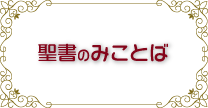ただ今、ルカによる福音書9章46節から48節までをご一緒にお聞きしました。46節に「弟子たちの間で、自分たちのうちだれがいちばん偉いかという議論が起きた」とあります。
ここに記されている弟子たちの姿は、どことなく滑稽なものに思われるかも知れません。主イエスは既に、御自身がこれから受けられる十字架の苦しみについて、弟子たちに明かしておられます。今日聞いている直前の箇所においても、44節で「人の子は人々の手に引き渡されようとしている」と、本当のことを打ち明けてくださっています。主イエスはこの時、既に、十字架にお掛かりになるメシアとしてエルサレムに向かってゆこうとしておられます。
ところが、その主イエスのすぐ傍に親しく寝起きしている弟子たちの心の内にあったのは、自分たちのうち、だれが一番偉いかという思いでした。しかもこのことを、自分一人の心の中だけに秘めておくというのではなしに、おおっぴらに言葉に出して互いに議論を始めたと言われています。彼らには、主イエスのありようが見えていません。御自身がこれから世の人々の罪を引き受けられ、その罪を御自身の身に負って十字架に掛かろうとしていらっしゃる主イエスの姿がまったく見えていません。自分たちの先生であり、メシア・救い主となってくださる方の進まれる方向がまったく理解できていません。
弟子たちのこういう無理解な姿を聖書から示されますと、ここにいる私たちとしては、ついひと言を掛けてあげたい思いを憶えるのではないでしょうか。即ち、「自分たちのうち、だれがいちばん偉いか」と議論し合って、互いに上を見上げ高ぶっている弟子たちに対して、「あなたがたは、もう少し平らな者になった方が良いのではないか。上ばかりを向こうとするのではなくて、主イエスが私たちの罪も、またあなたの罪も引き受けて十字架にお掛かりになり、厳しい神さまの裁きを受けて陰府の底にまで降ろうとしてくださっていることを、きちんと直視して受け止めることが大切ではないか」と、ついそのように弟子たちに忠告をしたいような思いを抱いてしまうのではないでしょうか。本当にそう思うのです。
主イエスは、まさに私たちのために十字架にお掛かりになり、非常に苦しんだ末にお亡くなりになり、陰府の深みにまで降ってくださるのです。そして、主イエスがそういうメシアとしての御業を果たしてくださるので、私たちは、たとえ自分自身の人生がどんなに深みに沈められたように感じる時にも、そこに主イエスがいてくださり、主イエスから明るい命の光が射し込むことを信じてよくされています。主イエスがまことに陰府の深みにまで降っていてくださればこそ、私たちには、慰めと主に信頼して生きる勇気と希望が与えられるのです。
そしてそうであれば、お互いの間でだれが一番偉いだろうかと議論して互いに高ぶっている弟子たちにも、「私たちに罪の赦しと自由を与えてくださる主イエスに目を留めることの大事さ」を分かっていて欲しいと思うのです。
今日の弟子たちの姿には、確かにそういう思いを憶えるのですが、また他方では、別の思いも浮かんできます。主イエスは確かに弟子たちのため、私たちのため、すべて信じる者のために御自身を空しくしてくださって、下方への道、陰府の深みにまで降ることになる道を辿ってくださるのですが、果たして私たちは、そういう主イエスの姿、主イエスの背中を追い続け、従ってゆくことができるのでしょうか。人生において、また互いの人間関係においても、私たちがしばしば経験するやっかいな事柄、苛立ちは、まさに私たちが下に向かってゆく道を歩みたがらないということから始まっているのではないでしょうか。そして、それがまさに私たちのありのままの姿であって、私たちそれぞれに抱えている自分固有の罪だと言えるのではないでしょうか。傲慢の罪、まさに傲慢な者に他ならないということが、私たちの本性ではないでしょうか。上から下に低い方へ低い方へと流れ下るのが水の本性であるとするならば、少しでも上へ上へと頭をもたげようとするのが私たち人間の本性ではないでしょうか。ここに語られている弟子たちの姿は、そういう人間の本性、私たちの正体を無防備に晒している姿だという風にも感じられるのです。
もちろん、私たちは自分の本性に逆らって、主に従って生きる者になろうと決心することはできます。けれども、それでも問題はなかなか容易に解決しないのです。私たちは自分自身の傲慢さというものを憎んで、それを水の中に沈めてしまおうとします。ところが私たちの傲慢さには、空気を一杯に含んだコルク栓のようなところがあって、決して水の中に沈みっ放しにならず、自分では水中に沈めたつもりでも、すぐに浮かび上がってきてしまいます。傲慢さの罪をどれだけ憎んでみても、それはどうしても一時的な見せかけの謙遜、欺瞞に満ちた偽りの謙遜にしかならないのです。私たちは所詮、そのような者ではないでしょうか。
そして、そういう私たち自身の正体に気がついた時に初めて、まさにそういう私たちのためにこそ、身代わりとなって御自身をささげてくださる贖い主が必要なのだということが分かってくるのではないでしょうか。46節の弟子たちの姿からは、そんなことを思わされるのです。
主イエスは、今申し上げたような人間の傲慢の罪という問題が、私たち人間にとってどんなに根深く、また手強い問題であるかをよく御存知でした。ですから、こういう議論が弟子たちの間で頭をもたげた時、その弟子たちに対して、それをたしなめられるのではなく、却って、慈しみの態度で接してくださいます。
主イエスは、近くにいた一人の幼な子を招いて、その子を御自身の傍に立たせておっしゃいます。47節に「イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、御自分のそばに立たせて、」とあります。主イエスは一人の幼な子と並んでお立ちになり、そして、おっしゃるのです。48節「わたしの名のためにこの子供を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである。あなたがた皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である」。何も考えずに読むと思わず読み飛ばしそうな箇所ですが、主イエスは幼な子と並んでお立ちになり、この子と主イエスは一緒である、等しいのだと、弟子たちに説明なさいます。主イエスはこの子と等しいと言う程に、御自身がへりくだられるのです。よく知られているように、フィリピの信徒への手紙には、「キリストが神と等しい身分でありながら、そのことにこだわろうとなさらず、却って身を低くしてくださった」と言われています。
私たちが人間である自分自身の本性からして、どうしてもしたがらないことを、主イエスはあえて実行なさいます。主イエス御自身は下へ降る道を辿られます。主イエスは幼な子と並んでお立ちになり、その身を低くするという点においては、まさに限界を設けられません。どこまでも低く、ひたすらに下の方、深みの底のところにまで降ってゆかれます。私たちは上への道を辿りたがります。しかし主イエスは下へ向かう道を辿られるのです。
「わたしの名のためにこの子供を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである」と主はおっしゃいます。ここでは「受け入れる」という言葉がくり返されます。「受け入れる」ということが大事なことだということでしょう。では、その「受け入れる」というのは、具体的にはどういうことなのでしょうか。これはまさに、ここに示されているような主イエスのあり方を受け入れるということ他なりません。まさに、「主イエスのようなあり方をするところにこそ、命の道があり、真理がある」ことを本当のことだと認め、そしてただ認めるだけでなく、私たち自身がこのようなあり方へと一歩踏み出し、歩み出すということでしょう。いみじくも、主イエス御自身がおっしゃっています。「わたしは道であり、真理であり、命である」。この主イエスに結ばれて下への道を辿るということ、それが主イエスを受け入れることに他なりません。
ヨハネによる福音書を読んでいますと、「キリストにある」ということが、ひっきりなしに語られていることに気づかされます。「キリストがわたしの内に」、また「わたしたちの内におられる主」という言い方がされるとき、ヨハネはいつもこんなことを考えています。一番有名ですぐに思い出されるのは、ヨハネによる福音書15章に出てくる「ぶどうの木のたとえ話」です。あのたとえ話の中で主イエスは「わたしにつながっていなさい。わたしもあなたがたにつながっている」とおっしゃった後、「人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないからである」とおっしゃいます。「キリストの内にあり、またキリストが私たちの内におられる」ということは、「キリストにつながって生活している」ということなのです。
この点は、使徒パウロも同じです。パウロはしきりに、自分は「キリストと共に死に、キリストと共に葬られ、そして、キリストと共によみがえらされている」ということを語ります。「わたしにとって生きるとはキリストである」とパウロが言う時には、今、申し上げたようなことをパウロも考えていたのです。即ち、枝が木の幹に結ばれて豊かに実を結ぶように、パウロもまた、思うようにゆかない時も、牢に閉じ込められたり鞭で打たれる時にも、どんなに苦労の多い人生を過ごしていると周りから思われるような時にも、自分はキリストと一つとされて生きているのだと考えていました。
パウロは多くの手紙の中で、自分のことを「キリストの僕である」と言い表すのですが、彼がそのように名乗る時、それは決して格好をつけてそう言っているのではなく、まさに「僕として主人のあり方に従って生きて歩んでいる」ことを述べています。
ところで、そのように主「イエスを受け入れる」ということ、「主イエスの僕として、キリストと共に死に、共によみがえらされて生きる」ということ、これは、信仰によってのみ可能となる生き方です。キリストにある小さな者となること、下へ向かう道を辿って生きることは、私たちの思いによっては不可能ですが、信仰によって生きるところでのみ可能です。キリストがどのような時にも共にいてくださるという信仰無しには、私たちは何一つできません。とりわけ、信仰無しには謙遜になるということは決してできません。主イエスを抜きにした謙遜は欺瞞にしかなりません。それは一時は良さそうでも、きっと悪しきものに変わります。
しかし、復活の主にいつも伴われて、その主への信仰によって謙遜になるということは、決して絵空事ではありません。主イエス・キリストに対する信仰から出る謙遜は、仕えるということ、実際の隣り人に仕える生活の中で具体的に現われます。
主イエスは今日のところで「わたしの名のためにこの子どもを受け入れる者は」とおっしゃいます。実際に、目の前にいる「この子」を受け入れるのでなくてはなりません。しかしそれは、実際に行われる時には、まことに地味な、隠れた働きになることでしょう。しかし、そういう隠れた小さな働きは、皆、主イエスが共にいてくださる信仰から出てきます。そして、私たちが、共に歩んでくださる主イエス・キリストを信じ、主にお仕えするつもりで一つ一つの業に励む時、主イエスはそういう生活を御覧になり、こんな風におっしゃることでしょう。「そのようにして、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々があなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである」と。
私たちが主に結ばれて主イエスの内にあり、主に属する者であるのなら、この週も、この聖書の言葉に教えられているあり方を、その道を、実際に辿っていきたいと願うのです。
主イエスは幼な子と並んでお立ちになり、この子供と御自身は等しいとおっしゃり、その子に仕えて生きてくださいます。私たちが小さい子供を前にする時に、未熟な者を前にしているのではなく、そこに主イエスが仕え、働いてくださっていることを憶え、私たちもまた、主と共に生きる者とされたいと願います。
主に伴っていただき、主イエスに結ばれて生きる生活の中で、僕としてのあり方を励まされ、強められたいと願うのです。お祈りをささげましょう。 |