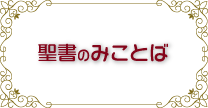ただ今、ルカによる福音書12章54節から59節までを、ご一緒にお聞きしました。新共同訳聖書では、2つの単元に分かれているように見出しが付けられています。それにつられて先週の週報には54節から56節と予告したのですが、今日の準備をする中で、この2つの記事はおそらく一つながりで意味をなしているようだと気づきましたので、今日は59節までの説教をいたします。
54節から56節に「イエスはまた群衆にも言われた。『あなたがたは、雲が西に出るのを見るとすぐに、「にわか雨になる」と言う。実際そのとおりになる。また、南風が吹いているのを見ると、「暑くなる」と言う。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか』」とあります。主イエスの厳しい言葉がけが印象に残ったという方がおられるのではないでしょうか。主イエスはここで「偽善者よ」と、大変厳しい言葉を掛けていらっしゃいます。しかし、ちょっと聞いただけでは、なぜ主イエスがこんなに厳しい呼びかけをしておられるのか、その理由が分からずに戸惑ってしまうということがあるかもしれません。一体なぜ、主イエスはこのように厳しい言い方をなさるのでしょうか。
「偽善者よ」と呼びかけられている人たちは、一体何をしたのでしょうか。ちょっと聞くと、別段何も悪いことはしていないような印象を受けます。ここで主イエスから厳しい言葉をかけられている人々は、いわゆる風読みをしているだけです。即ち、パレスチナの気候や風土の中で、天気がどのように移り変わるかということを経験則に照らして予想しているだけです。雲が西に見えたら雨になるから洗濯物を早目に取り込んでおこうとか、南の砂漠からの風が吹いてくることに気づいたら暑くなると予想しているだけです。取り立てて何も悪いことをしているようには感じられません。こういうことは、私たちも毎朝やっていることではないでしょうか。朝のテレビやラジオの天気予報を見たり聞いたりしながら、雨が予想されるのであれば傘の用意をするとか、気温が上がりそうであればエアコンのスイッチを入れておくとか、そういうことは私たちも日常的に行っていることだろうと思います。特に悪いことをしているとは思わないでしょう。
そしてそういう点では、主イエスも同意してくださるだろうと思います。主イエスが「偽善者よ」と厳しい口調で呼びかけておられるのは、私たちが風を読んで天気を予想するようなことについて非難しているのではなくて、私たちが行っていないこと、やろうとしないことについて、その姿勢を厳しく非難しておられるのです。「あなたたちは、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか」とおっしゃいます。主イエスが責めているのは、空や地の模様を見分けることではありません。そうではなくて、雨に濡れないようにというようなことは好んで一生懸命やるくせに、「今の時を見分ける」ことについては疎かにしている、「今の時を見分けようとはせずに、いい加減にしている」という点を、主イエスは厳しく追及しておられるのです。
「どうして今の時を見分けることを知らないのか」と主イエスは言われます。しかし、「今の時」とはどういう時なのでしょうか。「時を見分ける」とはどういうことなのでしょうか。「今の時」をどのように見分けるのでしょうか。世界中の様々な場所で戦争や災害のために傷つき苦しんでいる人がいることを聞いて心を痛めることが時を見分けることでしょうか。それともそういった厳しく困難なことが、今は自分の身の上に振り掛かっていないことを思って内心喜んだり感謝したりすることが今の時を見分けるということなのでしょうか。けれどもそうしたことはまさに、今の世界の中で同時に起きていることではないでしょうか。その土地、その場にいる人にとって困難と思えるような経験も、私たちの世界では、今同時に起こっているのではないでしょうか。そしてさらに踏み込んで言えば、そのようなこと、つまり良いことも悪いことも同時に起きているというのは、別に今の時代に限ったことではなくて、いつの時代も、世の中とはそのようなものではないでしょうか。
では「今の時を見分ける」とは、どういうことでしょうか。主イエス御自身は、今の時をどのような時であると思っておられたのでしょうか。今日の記事の少し先の箇所ですが、16章14節から17節で主イエスはおっしゃいます。「金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いて、イエスをあざ笑った。そこで、イエスは言われた。『あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存じである。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。律法と預言者は、ヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、だれもが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、律法の文字の一画がなくなるよりは、天地の消えうせる方が易しい』」。主イエスはここで、ヨハネまでの時とそれ以降の時を分けておられます。「律法と預言者はヨハネの時までである」とおっしゃいます。主イエス御自身はこういう思いをもって、「なぜ今の時を見ようとしないのか」とおっしゃっているに違いありません。
では、ヨハネまでの時とそれ以降の時というのは、どう違うのでしょうか。16章で主イエスが非難したように、ファリサイ派の人々は、自分たちの行いがどんなに聖書の律法に則っているかを人々に見せびらかして誇ろうとします。しかしそれは、本来の律法の目的からすると完全に倒錯した見当違いなあり方なのです。律法の行いをきちんと行うこと自体は決して間違ってはいません。むしろ、律法に従う生活が実際に営まれるのなら、それ自体は大いに願わしいことでもあるのです。ただし、律法の目的は人間が律法に従う生活を生きることで神の御名が贅美されるところにあります。しかしどうして、人間が律法に従うと神の御名が賛美され讃えられることになるのでしょうか。それは、律法が人間のあるべき正しいあり方を教えてくれているからです。もし本当に律法に従う生活を生きることができたなら、その時その人は幸いなあり方をするようになるのです。そして、そういう生き方に導いてくださった神に感謝して、心から神を讃えるに違いないのです。
そういう、本当に清らかで正しいあり方を人間がするための道しるべとして、律法は与えられているものなのです。
ところが、そういう本来は望ましい生き方を指し示す道しるべである律法に則って生活しようとすると、そこから逸れてしまうようなところが、どうしても私たち人間にはあるのです。従って、本来の望ましい生き方を表す道しるべ、あるいは設計図のような律法に照して私たちの生活を測ってみると、歪んだ箇所や、正確には律法に従いきれていないところが、どうしても出てくることになります。
ファリサイ派が倒錯している点は、主に2点あります。まずは、律法に対して自分のあり方が歪んでいたり正確には行えていないとしても、それには目をつぶって直視しようとせず、誤魔化しの中に生きてしまうところです。従って主イエスは、そのようファリサイ派的な生き方を偽善であり誤魔化しであると言って、大変嫌われました。しかし、ファリサイ派の偽善はそれだけではありません。十分に律法に則ったあり方ができていないにも拘わらず、そういう自分のあり方と他の人たちのあり方とを比べてみて、いかにも自分たちのあり方の方が正しく完全なあり方であるかのように感じ、自慢してしまう、そういう高慢なところがファリサイ派にはありました。そういうファリサイ派の高慢なあり方を鋭く捉えて、主イエスは、「あなたたちは自分の正しさを見せびらかしている」とおっしゃるのです。そして、「神さまはあなたたちの心を御存知である」とおっしゃいます。彼らは、律法を完全には行えていないくせに、他の人々よりはマシであると自分のあり方については勝手に大目に見た上で、そういうあり方をしている自分は当然神に受け容れられるべき者だと思って独り善がりな正しさを見せびらかしています。「他の人たちは、そういうあなたたちのあり方を立派なものだと考えて尊んでくれるかもしれないけれど、神さまは違う。人の目に値高く見られるものは、神さまには忌み嫌われるのだ」と、主イエスはおっしゃいました。
そして、そういう倒錯したあり方が通用するかのように思われてきたのは、ヨハネの時までだと、主イエスはおっしゃいます。どうしてヨハネの名前がここに出てくるのでしょうか。それは、ヨハネが当時の人々の間にはびこっていた安直な物の考え方を厳しく指摘したからです。ヨハネはこう教えました。「蝮の子らよ、差し迫った神の怒りを免れると、だれが教えたのか…我々の父はアブラハムなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでも、アブラハムの子たちを造り出すことがおできになる」。
即ち、「自分たちは全員、神さまの前には罪人なのだ」という大変に険しい理解が、ヨハネにはありました。ファリサイ派の人たちが中途半端に自分たちの律法違反には目をつぶって、他の人よりはマシであると安直に考えていた考え方を、ヨハネは一切認めなかったのです。従って、「律法と預言者を行え」とか「行うことができている」とか言って独り善がりな正しさの中を生きてきた時代は、ヨハネによって幕を閉じたのだと、主イエスはおっしゃるのです。主イエスが考える「今の時」というのは、ヨハネによって人間の安直な正しさが批判され非難され、認められない時が来ているということです。ファリサイ派的な中途半端に誤魔化すことで神の御前を生きていけるように思う偽善がもはや通用しなくなっている時代です。「自分たちはアブラハムの子孫なのだから、神が大目に見てくださるだろうとうそぶいて、平気で神抜きに生きてしまうことはもはや通用しない。そういう時が今、来ているのだ」と、主イエスはおっしゃるのです。「空模様を注意しながら、雨が降りそうならあなたがたは傘の仕度をするではないか。南から砂嵐がやって来そうだと思うなら家に閉じこもって対策をするではないか。それなのにどうして、『神の前に正直でないと、斧が根元に置かれていて切り倒されそうだ』とヨハネが警告してくれたのに、あなたがたは神の事柄については無頓着なのか」と、主イエスはおっしゃるのです。
ですから54節から56節の言葉は、当時のファリサイ派的な偽善を戒めて非難している言葉であると同時に、これは私たちに対しても語られている大変厳しい警告の言葉と言えます。「あなたは自分の胸に手を置いて、よく考えてみるがよい。ヨハネが警告したような安易なあり方を、あなた自身もしているのではないか。即ち、神さまの御前で熱心に神さまに従うように生きて、そのことで神さまの正しさを実感させられ心から喜んで生きるようなあり方をするのではなくて、神さまに背を向け神抜きの生き方を平気でしていながら、『わたしは神さまに従うのだ』と言っていれば、神さまはきっと大目に見てくださるに決まっているというような、手前勝手な考え方をしているのではないか」と、主イエスは私たちにも今日のところで語りかけておられるのです。
そして、そこまでで今日の話を終えるわけにはいかず、どうしてもその先の言葉を聞かないわけにはいかないのです。従って今日は、59節まで聞かなくてはなりません。
主イエスはおっしゃいます。57節に「あなたがたは、何が正しいかを、どうして自分で判断しないのか」とあります。「空模様であれば、あなたは当然のように判断して雨が降りそうなら雨具を持参する。それなのにどうして、ヨハネがあんなにも親切に警告してくれたのに、神の裁きについては『そんなことは起こりっこない』と決めて、神の御前で自分は本当に正しくあろうとしているかどうかということを判断しようとしないのか」と、主イエスはおっしゃっているのです。「間違ってはいけない。神さまは侮られるようなお方ではない。あなたが今生きている人生の時は、終わりの裁きに向かっての道のりを歩いているのだ」、「あなたは今、まさに神の御前に訴えられる者として人生を生きている。あなたの罪を指摘し、あなたの人生の生き方が正しくないと訴えようとする者が、あなたと連れ立って道を進んでいる。もしあなたが今のまま、神の裁きについて甘く考えたまま道を進むなら、それは大変深刻な結果をもたらすに違いない。あなたは厳しく裁かれて牢につながれてしまうことになる」と、主イエスは警告しておられるのです。
今日のこの箇所は、主イエスが「群衆たちに向かっても」語られたと記されています。これまでは弟子たちに向かって教えておられたのですが、ここでは「群衆にも」と言われていますから、これは群衆だけを非難しているのではなくて、弟子たちにも群衆にも話しておられるのです。どうしてこういう言い方になるのかというと、ここに述べられている警告が、弟子にも群衆にも、すべての人に当てはまることだからです。私たちはこの地上の命の最後には、誰であれ、神や主イエスを知っていても知らなくても、自分がどういう人生を生きたかということが問題になる時が来るのです。
今日の箇所では、神の裁きについて安易に考えてしまうことについて、はっきりとした警告が主イエスから語りかけられているのですですが、このように警告されても、私たちとしては困ってしまうのではないでしょうか。主イエスだけでなく、その前には洗礼者ヨハネも警告してくれたように、私たちには神との関わり方、あるいは神の御前に命を与えられて生きている者としての責任という点で、いい加減になってしまうところが確かにあるのです。
ヨハネは、そんな私たちの中途半端なあり方が神の御前には決して通用しないことを教えてくれました。しかしそういうヨハネの言葉を聞いて、実際のところ私たちはどうすれば良いのでしょうか。聖書の言葉に耳を澄まして、神の御心に適うことは何であるか注意深く考えてそれに従って生活するのが良いのでしょうか。しかし、たとえ私たちがそれをどんなに真剣に、慎重に行なったところで、やはり私たちもファリサイ派のような中途半端さをどうしたって抱えざるを得ないのではないでしょうか。
また主イエスは、なぜ今日のような警告を弟子たちや群衆に向かってお語りになったのでしょうか。それは、主イエスがこれから進んで行かれる十字架への道行がどうして起こるのかということを教えようとしておられるからです。私たちは自分自身のありようを考えるならば、ヨハネの警告したとおり、「斧が木の根元に置かれている。あなたがたが正しいあり方ができないならば、斧で木が切り倒されるように、あなたがたは滅ぼされる」のですが、たとえ私たちが滅ぼされたとしても、神に対して文句を言うことができない、本来のあり方から倒錯した生き方をするようなところが、私たちにはあるのです。
しかし、そのような私たちが最終的に受けなくてはならない罪の報いと滅びを、主イエスが代わって御自身の身の上に引き受けてくださり、十字架にかけられて死んでくださったのです。主イエスが今、エルサレムに向かって行って十字架にお掛かりになる、その歩みが、まさにそういう人間の罪を清算するためのものなのだということを、この日主イエスは、すべての人に向かって語ってくださったのではないでしょうか。
そして、すべての人に向かって語っておられるということは、十字架による罪の赦しに与ることができないような人は、誰一人いないということではないでしょうか。主イエスに熱心に従おうとする人たちだけが罪の赦しに与るのではないのです。これまでどんなに主イエスに対して背中を向け、神抜きで生きてしまった人であっても、主イエスの十字架による赦しの御業は確かにその人のためにも行われるのです。十字架というのは、私たちがそれを強く思えば事実であり、忘れたり無視をすれば消えてなくなるようなお伽話ではありません。たとえ私たちが無視しても、忘れていても、十字架はゴルゴタの丘に確かに立てられ、主イエスがそこに挙げられ、苦しんで亡くなられたという地上の事実は消えてなくなることがないのです。事実として、十字架の主の苦しみと死によって、私たちの罪は清算されているのです。
問題なのは、その主イエスによる罪の赦しとは別に、私たちが自分好みのいい加減な赦しの気分の中に生きてしまうことなのです。私たちが自分勝手に生きてしまう時には、そこには本当の赦しはありません。それは中途半端に私たちが自分のことを甘く考えて、自分は大丈夫だと言っているに過ぎないからです。私たちの罪を清算するために、主イエス・キリストが十字架に向かって歩んでくださったのです。
ですから私たちは、確かに主イエスの十字架にとりなされて罪の赦しの下に生かされているのだということを知らなくてはなりません。最後の1レプトンに至るまで、主イエスは完全に私たちの身代金を支払って、私たちを罪の奴隷の牢屋から助け出して、主イエスのものとして生きるように、新しい命を与えてくださっているのです。
私たちは、地上を生きることを許されている、与えられている時間の限り、与えられているすべてをささげて主イエスの救いに感謝し、主に仕える僕としての生活をここから歩んでいく、そのような幸いな者とされたいと願います。お祈りをささげましょう。 |