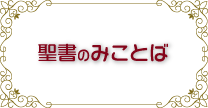ただ今、ルカによる福音書13章1節から9節までを、ご一緒にお聞きしました。
1節に「ちょうどそのとき、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜたことをイエスに告げた」とあります。ここに述べられている「ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜた」という出来事は、残念ながらあまりはっきりしたことが分かりません。聖書のここに書かれている以外に、こうした事件があったことを伝える別の記録が見つかっていないためです。ここに名前が出てくるピラトは、3章1節でユダヤの総督として赴任していたことが述べられているポンティオ・ピラトです。後に、主イエスに十字架刑を言い渡す人物です。今日の記事によれば、そのピラトがガリラヤの人々に何らかの理由で弾圧を加え、血が流されて命が奪われるという事件があったようなのです。ただし、このことを裏付ける記録がどこかに存在するわけではありませんので、何年何月何日の出来事であったとか、どんな状況であったとかまでは詳しく言うことはできません。しかし、仮にこのようなことが本当に起きていたのであれば、当然のことですがガリラヤの人々は激しい衝撃を受け、ピラトに対する反感と怒りが一気に吹き出したであろうと思われます。
主イエスの許にこの事件を知らせに来た人は、主イエス御自身もガリラヤのナザレ出身なので、自分たちと同じようにピラトの暴挙に対して大いに憤慨してもらおうと思って、この知らせを伝えたようです。この人は、ピラトのことを憎む人たちがいかにも取りそうな行動をしているのです。
ところで、主イエスはその知らせを聞いて、事件を伝えにやって来た人たちの予想とは少し違った受け取り方をなさいました。もちろん主イエスも、この事件が痛ましくピラトの行いが憎むべき暴挙であると思っておられたでしょうが、しかしそれ以上に、この事件で亡くなった人々やその人たちの近親を思いやって、おっしゃいました。2節3節に「イエスはお答えになった。『そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い者だったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる』」とあります。主イエスは、「この度のように思いがけなく痛ましい出来事に遭遇すると、多くの人たちは辛い思いをした人に同情して、何故こんなことが起こったのかとその理由を聞きたがる。ガリラヤの人々が無惨にも殺されてしまった知らせをもたらした人たちは、この責任はローマ総督のピラトにあると思って憤っている。しかしそこには、自分自身への顧みが欠けているのではないか」とおっしゃるのです。
12章の終わりの箇所で、主イエスは人々に「あなたがたは、何が正しいかをどうして自分で判断しないのか」とおっしゃっておられました。ということは、判断する力が一人ひとりに備わっていたと、主イエスは信じておられたことになります。「ピラトはけしからん。断固として反対すべき」と気勢をあげる人々は、自分の考えからそう言っているわけではありません。どこからか聞かされ吹き込まれた事柄を、いつの間にかまるで自分自身の意見であるかのように思い込んで話しているに過ぎません。
しかし主イエスは、ガリラヤの人々が命を奪われた痛ましい出来事を通して、一人ひとりが本当に向き合うべき事柄を分からせようとなさいます。そしてそのために、告げられたこととは違う、もう一つの出来事をお示しになります。これも痛ましい出来事です。4節に「また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか」とあります。主イエスは、その場にいた人々に向かって問いかけられます。当時、エルサレム市内にあったシロアムの塔が、これも正確な原因までは分かりませんが、大風が吹きつけたためか、あるいは老朽化していたために倒壊してその下敷きとなって亡くなった人々がいたようなのです。この事件でも人命が失われるという痛ましいことが起こります。ただしこちらの事件では ピラトが殺害を命じたような悪意が関わっていません。思いがけなく生じた激しい気象状況のために起こった事故です。
主イエスは、ガリラヤの事件とシロアムの事故を並べてお語りになり、その上で一つのことをお尋ねになります。「犠牲になった人々が、他のどの人よりも罪深い者だったからこのような出来事の犠牲者になったのだろうか」と。そして「決してそうではない」とおっしゃいます。5節に「決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる」とあります。この5節の言葉は、3節の言葉と全く同じ言葉です。主イエスは人々に向かって、「あなたがたも悔い改めなければ、誰もが滅びることになる」とおっしゃるのです。
「誰もが滅びる」ということは、主イエスのこの言葉は、私たちにも向けられている滅びの宣告でしょうか。決してそうではありません。「あなたがたは、何が正しいかをどうして自分で判断しないのか」とおっしゃる主イエスが、「あなたには正しい判断ができるはずだ」と信頼して語っておられるのと同じように、今日の3節や5節でも、「痛ましい出来事を見聞きした人々が正しい判断をして悔い改めることができるはずだ」という信頼のもとに、主イエスはこの言葉を語っておられます。3節と5節の言葉は、私たちを滅ぼそうとして、滅びに定める宣告をしているのではなくて、悔い改めへの招きとして語られている言葉です。
主イエスの時代に限らず、世の中には、ガリラヤの人々が経験させられたような悪意による流血のニュースに出遭うと、そのことに憤慨、自分できちんと原因を調べないままに、原因となったと思われる人を悪く言ってしまう場合が少なくありません。またシロアムの塔のような災害のニュースに接すると、今度は亡くなった人や傷を負った人を気の毒に思って同情するという場合が多くあります。中には、似たような不幸な出来事が自分の身にも起こるのではないかと感じて、不安や恐れを感じる方がいらっしゃるかもしれません。
けれども、主イエスはここで、いたずらに人々を怖がらせようとしておられるのではありません。そうではなくて、「正しい判断をして悔い改めに生きるようになること」を願って、語っておられます。今日ここに並べられた事件のように、もしも今日ここで突然に命が終わるようなことが起こるとしても、その時にこそ神に信頼し、自分自身をすべて神にお委ねして生きることこそ、主イエスはお求めになるのです。迫害や弾圧、戦争や天変地異などで無惨にも命が失われてしまう出来事を見聞きしたなら、自分自身もその同じ命を、明日をも知れぬ命を生きていることを思って、今生きているこの時に、神の御前に生かされている者としてのふさわしいあり方をとるようにと、おっしゃるのです。自分の命だけは、人生の道半ばで失われていった人たちとは別だと思って、その起こった出来事の責任を追及したり亡くなった人を憐れんだりすることは、実は、目の前に起きている出来事が決して自分の身の上には起こらないことだと、楽観的に受け取っている姿に他ならないのです。
そしてここまで考えてくると、今日の主イエスの言葉は、「何が正しいかを自分自身で判断するように」という招きであると同時に、もう一つ前のところでおっしゃっていた「あなたがたは、どうして今の時を見分けないのか」という招きにもつながっていることが分かってくるのではないでしょうか。「今の時」がどのような時であるのかは、前回の説教でも申し上げましたが、主イエスは洗礼者ヨハネまでの時とその後の時とを分けてお考えになります。そして、「今の時」というのは、ヨハネが宣べ伝えた「神の国がやって来る」という知らせが主イエスによってまさに実現している、そういう時です。主イエスがこの地上にやって来てくださり、私たちに出会い、「わたしについてきなさい」と呼びかけてくださり、私たちを悔い改めへと導こうとしておられる、それが主イエスのおっしゃる「今の時」です。
「あなたがたも悔い改めなければ皆同じように滅びる」という言葉は、滅びないために、主イエスの言葉を聞き取って「今日ここから生きていくように」という招きの言葉です。主イエスは私たちが滅びるのではなくて、悔い改めへと導かれ、主の民の一人となって生きることを願っておられます。
その証拠に、主イエスは今日の2つの警告に続けて、「一人の情け深い園丁のたとえ話」をなさいます。6節から9節です。「あるぶどう園にいちじくの木が植えられていた」と話が始まります。ぶどう園なのに何故いちじくの木が植えられていたのかと不思議に思うかもしれません。主イエスの時代のぶどう園には、このような光景は見られていたようです。なぜかというと、ぶどうは蔓で柱に巻きついて育ちます。今日だとV字形のコンクリートの支柱がよく見られますが、昔はあの支柱の役目をいちじくの木が果たしていたようです。それで、ぶどう園にはいちじくの木がよく見られました。
ところで、このたとえに出てくるいちじくの木は、実を求めても目指す実りが一向に見当たりません。それでぶどう園の主人は、この実を結ばない木を切り倒すように園丁に言います。6節7節に「そして、イエスは次のたとえを話された。『ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで、園丁に言った。「もう三年もの間、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくのか」』」とあります。このたとえ話で、今にも切り倒されそうになっているいちじくの木は、神がいくら忍耐して待ち望んでも葉ばかり繁らせて一向に実を結ばずにいながら、それでいて自分たちは「これで正しい」と言い張っている、神の民イスラエルを表しています。洗礼者ヨハネも、こういうイスラエルのあり方に対して、「斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆、切り倒され火に投げ込まれる」と警告をしていました。まさにこの警告どおりのことが、このたとえ話の中で起こると言われています。
さて、考えなくてはならないのは、切り倒されそうになっている木のことです。この木とは、主イエスに反対し陰謀によって亡き者にしようと企んだ人たちのことでしょうか。もしそうだとしたら、洗礼者ヨハネは、洗礼を受けようとしてやって来た人たちに「斧はすでに木の根元に置かれている」という警告をする必要はなかったはずです。なぜなら、主イエスに敵対する人たちは、ヨハネのところに来てはいないからです。「自分は正しい」と思っている人たちはエルサレムにいます。ヨハネのところに来た人たちは、「自分たちは悔い改めなければならない」と思っている人たちです。ヨハネはそういう人たちに向かって警告を語りました。ということは、この警告は、主イエスに敵対している人たちに向かってだけではなく、主イエスの弟子たちも含めて、すべての人間に対して語られているということになります。主イエスの弟子たちも例外ではありません。実を結ばない木は皆、遂には切り倒されて滅んでしまう、それがこのたとえの中で語られていることです。
ところで、園丁は答えました。8節9節に「園丁は答えた。『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒してください』」とあります。いちじくの木はこのままで良いのだとは、主イエスはおっしゃいません。けれども園丁は、「最後にもう一年、肥やしをやってみます」と答え、そして「それでも駄目なら、切り倒してください」と答えました。
いちじくの木が神の民イスラエルであるのなら、この園丁は一体誰でしょうか。「3年の間、実を結んでこなかったけれども、最後にもう一度待ってほしい。この一年のうちに肥やしをやってみるから」と、ぶどう園の主人に願うこの園丁とは誰で、何のことを言っているのでしょうか。
主イエスが地上で神の国を宣べ伝えられた公生涯の歳月は、およそ3年であったと言われています。「もう3年もの間、実を探しているのに見つかったためしがない」と、ぶどう園の主人が述べている期間は、主イエスが神の国の訪れを宣べ伝えて地上を歩まれた年数と重なります。そしてその3年の間、目ぼしい実りは無かったと言われます。だから「この役に立たない木を切り倒せ」と、神はおっしゃるのです。これに対して、園丁は「最後にもう一年だけ待ってください。今年は穴を掘って肥やしをやってみます。それでも駄目なら切り倒してください」と言っていますが、園丁の言う「最後にもう一度、肥やしをやる」というのは、主イエスがこれから向かって行くエルサレムで果たそうとしておられる「十字架の御業」のことではないでしょうか。園丁はいちじくの木の周りに穴を掘り、木の根がきっと吸収してくれることを信じて、そこに肥やしを入れます。いちじくの木が実りの無いままに滅んでしまうのではなく、木が根から栄養を吸収して実をつけるだけの活力を与えようとします。この園丁は、自分自身を栄養として与えるために穴を掘り、自らをそこに沈めようとしているのです。
キリストの十字架は、私たちの罪の身代わりとして主イエス御自身が身をささげ、罪を贖って清算してくださった出来事であると言われます。しかしそれは、単なる清算ではありません。私たちの罪が十字架の上で清算され、私たちの罪が無くなったということで終わる話ではないのです。主イエスは、私たちが神に喜ばれる者となるように、実を結ぶように、御自身が深く陰府にまで降り、御自身が肥やしとなり、栄養と活力を私たちにもたらしてくださるのです。それが、この園丁のたとえ話です。
「あなたがたも悔い改めなければ、皆滅びる」と二度重ねて警告なさった直後に、この園丁の話がされている点に注目したいのです。このいちじくの木は盛んに葉を繁らせ、健康的に育っているつもりでいます。ところがそこには、本来生まれて当然の実りが見当たらないのです。それは、この木が神の御心をたずね求めて従おうとしないで、自分の行いの見事さや自分の利益にばかり思いが向かっているからではないでしょうか。
しかし、切り倒されても仕方ないようなあり方をしているいちじくの木のために、主イエスは穴を掘り、そこに肥やしを入れ、信仰の実りが生まれるように配慮してくださいます。これは大変不思議なことですが、このいちじくの木はぶどう園の中に植わっています。「わたしはまことのぶどうの木」と言ってくださる方が、いちじくの木のために、自らを穴の中に沈めようとしてくださるのです。当時、いちじくの木はぶどうの支えになっているものですが、このたとえ話の中では、「まことのぶどうの木」が栄養の源となって、いちじくの木を支えてくれるようになるという話です。
主イエスは穴を掘り、そこに栄養を入れて、信仰の実りが生まれるように配慮してくださいます。木の根がきっと栄養分を吸い上げ、命を生き、実りを生む活力にしてくれるに違いないと信じて、主イエスはエルサレムに向かい、御自身の御業を果たしてゆかれるのです。
世の中に起こる痛ましい出来事に同情したり、不当な暴力に対して憤ることは、決して悪いことではありませんし、間違ってもいません。しかし、ただそれだけであってはなりません。私たちは、自分自身の、いずれ失われるに違いない命の状態にも心を向け、気を配るようでなくてはなりません。一人一人が神から命をお預かりして、今この地上を生かされているからです。
主イエスが御自身の身を与えて栄養としてくださる、その栄養をいただいて力づけられ、義の実を結ぶ生活へと育てられたいと願います。お祈りをささげましょう。 |