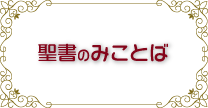ただ今、ルカによる福音書13章10節から21節までをご一緒にお聞きしました。10節に「安息日に、イエスはある会堂で教えておられた」とあります。安息日に会堂に入って人々を教えたことは、主イエスにとっては特別なことではなかったようです。この福音書の4章14節15節に「イエスは“霊”の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸会堂で教え、皆から尊敬を受けられた」とあります。主イエスの活動の初期、まだガリラヤにおられた時から、主イエスは安息日になると会堂にお入りになって人々を教えておられました。今日の記事の箇所では、主イエスはもはやガリラヤにはおられません。エルサレムを目ざして、それも、エルサレム郊外のゴルゴタの丘に立つ十字架の方に顔を固く向けて旅をしておられます。しかしその道中にあっても、安息日になると主イエスは会堂にお入りになり、いつもと変わらないように人々を教えられたのでした。
今日はまずこの点について聞き取りたいと思います。主イエスが安息日毎に、当時の会堂で持たれていた礼拝に参加しておられたことは、私たちにとっては大いに心強められることであると言えるのではないでしょうか。
主イエスは神の独り子なのですから、御自身が会堂においでにならなかったとしても、むしろ、神にまっすぐに向かって礼拝をささげたいと思う人たちが主イエスを尋ね求め、主がおられる場所に集まって来るというあり方も、可能性としてはあり得たに違いありません。もし主イエスが本当はどなたであるかということを知る人がいたならば、積極的に主イエスのおられる場所にやって来るというあり方の方が、本来のあるべき姿であると言えるかも知れません。その意味では、主イエスは人々が御自身の許に集まって来るのを待つということだって考えられたのでした。ところが、それはあくまでもそう考えることもできるという仮定の話であって、現実の主イエスは毎週安息日毎に会堂にお入りになって、人々の礼拝に参加され、神の事柄をその場にいる人々に説き明かしておられたのでした。
これは、主イエス御自身が神を礼拝しようと集まって来る民を求めてくださっている、そういう姿です。主イエスは、礼拝をささげて神の前にひれ伏し、神の言葉を聞いて力づけられ御心に適う歩みを始めたいと願う群れを、またそこにやって来ようとする一人ひとりを求めておられ、御自身も自ら神の民の一員となって御言葉を説き明かし、告げ知らせようとしてくださるのです。
こういう主イエスのお姿を聖書の中に発見する時、私たちは大いに励まされ、勇気を与えられるのではないでしょうか。主イエスは私たちが礼拝をささげる安息の日に、決して一人孤高の方として、私たちのありようを冷ややかに見降ろしておられるのではありません。むしろ主イエス御自身が進んで礼拝に参加してくださり、礼拝に集まる人々の間に共にいようとしてくださるのです。主イエスがそういう方でいらっしゃるのならば、主は聖書の中にだけおられるのではなくて、今日私たちが礼拝をささげ、御言に養われ慰めと励ましを受けてここから歩んでゆきたいと願うこの場所にも伴ってくださることを信じて良いのではないでしょうか。主が安息日毎に礼拝する民を求めてくださり、その中にお入りになり、御自身が礼拝の民の一人になってくださる事実は、そんな風に今日この礼拝に集っている私たちを慰め勇気づけてくれるのです。
ところで、この日主イエスが参加した礼拝の場で、主イエスは一人の女性を見出されました。長年にわたって病気に苦しめられ、不自由な生活を余様なくされていた人だったと言われています。11節に「そこに、十八年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったまま、どうしても伸ばすことができなかった」とあります。この女性が何歳であったかは記されていないので分かりません。けれども当時の平均寿命はそんなに長くなく、50歳手前ぐらいがせいぜいだったろうと言われていますので、18年間病気を抱えていたこの人は、人生の半分くらい腰が曲がった状態で過ごしていたものと思われます。
この人は、自ら癒やされたいという願いを持って主の許にやって来た訳ではないようです。もしそういう願いを持ってやって来ていたならば、会堂に主イエスが入って来られた時、真っ先に主の前に進み出て足許にひれ伏し、癒してくださるように願ったはずだからです。けれども、そうしたことは何も起こらないまま、礼拝のプログラムは進んで行きます。主イエスが会堂の中で立ち上がり、前へと進んで、そこに集まっていた会衆に向き直り御言を語ろうとした、その時に主イエスはこの女性を御覧になっています。ですから、礼拝はいつも通り進んでいました。この女性は体の不自由さを抱えていましたが、自分の癒しを期待した訳ではなく、礼拝に参加したい一心でこの場にやって来ていたものと思われます。主イエスはそんな女性を御覧になり、目を留められたのでした。
主イエスが目を留めたこの女性についてもう少し踏み込んで考えますと、おそらくこの人は、会堂の前の方や真ん中ではなくて、後ろの隅の方に座っていたのではないでしょうか。当時の多くのユダヤ人の考え方からすると、長期にわたる病気は、周りの人には分からないけれども、何らかの罪を本人かその縁者に当たる者が犯していて、それに対する神の裁きが現れていると思われていました。この人は、男性ではなく女性でした。安息日毎に神の前にやって来て御言に励まされ生きたいと願っている、この人は神に向かおうとする姿勢が確かにあったのですが、しかし同時に、なるべく目立たないように密やかに礼拝をささげていたものと思われます。今日でも、こういう方はいらっしゃるのではないでしょうか。毎週きちんと礼拝においでになるのですが、後ろの方の席や柱の陰などの、あまり人目につかないような席を選んで座るような方がいらっしゃいます。
ところが主イエスは、そういう一人ひとりにも目を留めてくださるのです。それどころか、この人が長年にわたって苦しんできたことを即座に見て取り、御前に呼び寄せて癒やされるのです。12節13節に「イエスはその女を見て呼び寄せ、『婦人よ、病気は治った』と言って、その上に手を置かれた。女は、たちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した」とあります。何とも不思議ななりゆきですが、礼拝の席では時折このようなことが起こります。主イエスが礼拝に集う人々のただ中に来てくださるためです。もしかすると、礼拝の中で癒やされたり力を与えられたりする出来事は、多くの人が黙っているために分からないだけで、実際には私たちが想像する以上にしばしば起きていることかも知りません。
たとえば私自身の経験では、礼拝が終わった時にある方に呼び止められて、「先生は先週のわたしの生活をどこかで見ていたのですか」と聞かれたことが、これまで何度かありました。私が見ているはずはないのです。隠れて教会員の生活を見て回るほど、愛宕町教会の生活は暇ではありません。私としては、その日に与えられた聖書の御言を何とかして聞き取り、そして自分に聞き取れた範囲のものを、その日の御言として皆さんに話しているだけのことです。
けれども、主イエスは確かに教会の礼拝の中にやって来てくださるのです。そして、真剣に御言に聞いて支えられたいと願い、主イエスによる罪の赦しを求めて集まって来る人たちを御覧になってくださるのです。一人ひとりが捕らえられている思い煩いや痛みの事柄に主イエスが触れてくださって、「あなたの罪は赦された。今日ここからもう一度、新しくされた者として歩み出しなさい。身を慎んで、今からは祈りをもって清くされた者としての生活を歩みなさい」と招いてくださいます。礼拝の中で、そういう主イエスの招きを自分の事柄として経験すると、その人は何となく、牧師が自分の生活をどこかで観察していたような気持ちになるのです。しかし実際には、それは牧師ではなくて、主イエスがその人を御覧になっているのです。
今日の箇所でも「イエスはその女を見て呼び寄せ、その上に手を置かれた」と言われている通りなのです。人間にできることはまことに僅かです。ですが、主イエスが礼拝する者を求めてそこに来て働いてくださる時には、まことに大きな喜ばしい結果が生まれるのです。この女性は、自分ではまったく予想していなかったことですが、思いがけず腰が真っ直ぐに伸びて、心から神を賛美するように変えられたのでした。主が触れてくださる以前には、自分の腰が癒やされて真っ直ぐになる日がやって来るとは、まるで予想していませんでした。これまでの18年間と同じように、これからの日々にも体の不調と痛みがついて回るに違いない、それが自分の一生なのだと思い込んでいました。しかし、そこに主が踏み込んで来て親しく御言を語りかけ、痛みに触れてくださったことで、まことに思いがけない癒しがもたらされました。この人とすれば、真っ直ぐにされた腰で立ち上がり、神を賛美せずにはいられないのです。
主イエスが私たちの許を訪れてくださり、感謝するしかない御業を行ってくださるところでは、今日の記事に証しされているように、群れの中から繰り返し、喜びに溢れた賛美の声が湧き上がります。
しかしそれと並んで、そのような喜びに冷や水を浴びせかけ、それを人間の決まりごとのように言おうとする人も現れます。今日の箇所では、この会堂の礼拝に責任を負う立場にあった会堂長が、ここで起きたことに異を唱えようとしています。彼はこの会堂の管理者であり、礼拝を取り仕切る責任者です。この会堂にやって来た旅行者である主イエスに前に出ることを許して話をさせたのも、この会堂長でした。そして、その彼の立場から言うと、本当に思いがけないことがこの日の礼拝の中で起きてしまったのでした。会堂長とすれば、この日やって来た旅人たちを代表して主イエスを前に立たせ、そこで、二言三言当たり障りのない挨拶をしてくれれば良かったのです。まさか、体の不自由な女性を前に進ませ会衆の面前で癒しを行うとは、つゆ程も思っていませんでした。ところが実際に女性は癒やされ、神の憐れみと恵みを心から賛美する出来事が起きてしまったのです。
この会堂長は、癒やされた女性を注意することができません。彼女はただそこにいて癒やされただけで、安息日の規定に触れるようなことは何もしていないからです。では、癒した側の主イエスを咎めるのでしょうか。それもできません。神の力に満ちた慈しみの出事を、今この場にいた皆が目撃して、主イエスへの驚きと尊敬の思いに満ちているからです。結局会堂長は、癒しの出来事の当事者ではなくて、目撃者たちに向かって、「このようなことは好ましくない。安息日は安息日らしく何の業も行ってはならない。働くべき日は6日あるのだから、その間に病気の治療を行うように」と語ったのでした。会堂長の立場からすれば、そう言うことで安息日の秩序を守っているつもりだったのでした。
ところが、この言葉が主イエスから大変厳しく反論されることになります。会堂長は、まるで風邪を引いていた人が治療を受けて簡単に治ったかのような言い方をしました。しかし主イエスはここで、癒やされた女性の中に、18年もの間サタンに組み敷かれて病気の状態に縛りつけられていたという現実を見て取っておられたのです。本当に長い間、この女性は辛さの中に置かれていました。病気が長びくことは、単に病んでいる以上に、神の裁きの下にその人があると思われるような出来事だったのです。この女性は、礼拝に出たいと思う、確かに神の民の一員です。であるならば、一刻も早くその身から病気の困難と屈辱を取り除いてあげなくてはなりません。この日に起きた出来事は、安息日の決まりを破った出来事ではなくて、むしろこの女性自身と癒しを目撃した人たちが、心の底から喜んで神の慈しみの豊かさと御力の大きさを誉め讃えたという出来事でした。それはまさに、安息日に人が神と共に、今日与えられている命を感謝し喜ぶような出来事でした。主イエスはその点を指摘して、ここで起こった出来事がまさに安息日に相応しい神の御業だったことを語ります。そういう反論をされて、会堂長や彼と似た考えを持つ人は恥じ入りましたけれども、より多くのこの日の出来事を目撃した人々は、神のなさりようを知って大いに喜んだのでした。
さて、このような出来事の直後で、主イエスは人々に神の国について教えられます。たった今見聞きした出来事は、まさしくこの会堂の中に主イエスがやって来てくださり、女性を長年にわたって組み敷いてきたサタンとの力比べをなさり、サタンの支配から彼女を解放して、神の御支配の下に移されたような出来事だったからです。ここに起こったこと、それはまさしく「神の国の訪れ」「悪が支配する状態に代わって、神の力が現れる」出来事でした。
これを別に言うならば、18節から21節にかけて語られている「からし種とパン種の話」は一般的なたとえ話として語られているのではないということになります。この会堂の中で実際に起こった女性の癒しの出来事の説明として、この2つのたとえ話は語られているのです。
主イエスがここでお語りになっているからし種もパン種も、どちらも目に見えない程小さいものを表しています。しかし、からし種もパン種もその内に命の力を秘めていて、やがて大きく成長することを語っています。18節19節に「そこで、イエスは言われた。『神の国は何に似ているか。何にたとえようか。それは、からし種に似ている。人がこれを取って庭に蒔くと、成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る』」とあります。からし種は本当に小さなものです。0.5ミリのシャープペンに力をかけすぎると芯が折れてしまうことがありますが、からし種の外見は、まさにそのほんのちょっと欠けた先、その芯とそっくりな大きさと色をしています。ところがその小さな種が地面に落ちると、大木に育つと言われます。2メートル半か3メートルくらいの木になって、高い安全な場所なので、その梢に鳥が来て巣を作りそこを宿り場にするのだと、主イエスは教えられます。
このことは、頭の中だけで空想して語っている言葉ではありません。神を真剣に礼拝しようと集まって来る人の間に主イエスもやって来て御自身も礼拝の民となってくださる、そのところで一つ一つ神の御業が行なわれ、御言が説き明かされて、そこに大きな喜びと賛美が生まれます。最初それは、ただ一回限りの小さな出来事であったかのように起こるのですが、主イエスが礼拝の中で共にいてくださるところでは、神の御業が次第に育って行くようになるのです。そして、最初からは思いもしなかったような堅固で力強い礼拝がささげられるようになります。そしてその礼拝の中に、外から来た人たちも加えられてゆくようになるのです。それがこのたとえの言っている意味です。空の鳥たちは、もともとからし種から育ったものではありません。よそからやって来て、梢を棲家として住み着くのですが、しかしそういうことは私たちの礼拝の場合にも当てはまるだろうと思います。この礼拝は、愛宕町教会の群れの中で信仰を与えられた者たちだけではなく、外から来てこの礼拝に加えられていく人たちもいるのです。そしてその人たちもこの群れを住まいとし、共に暮らす者たちとされてゆくのです。
もう一つのパン種のたとえは、成長の密やかさを教えています。20節21節に「また言われた。『神の国を何にたとえようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる』」とあります。パン種はイースト菌です。3サトンの粉とは、聖書の最後にある度量衡の表で見ると、およそ40ℓです。40ℓの粉でパンを作った場合、膨らむとどれ程の量になるか、とんでもない分量のパンが出来上がります。ある註解書の説明では、150人分以上のパンになると言われていました。からし種の場合には、からし種自体が芽を出し葉を繁らせて木になって行きますが、イースト菌の場合には、菌自体は発酵して分解してしまいます。そしてパン生地の中に姿を消していくようになるのです。主イエスが礼拝において一人ひとりに触れてくださり、力づけてくださる働きも、それ自体が残るのではなくて、御業に強められ慰められ、勇気を与えられた者たちが、信仰の歩みを確かにされてゆくという仕方で残っていくようになります。
ちょうど、エマオ途上で復活の主イエスと出会ったクレオパともう一人の弟子が、主が説き明かしてくださる御言に心を暖められ、そして、自分たちに御言を説き明かしてくださった方が主イエスなのだと分かった途端に、主が自分たちの前から姿を消して、二人の弟子たちの中に姿を隠して見えなくなったように、パン種もパン生地の中に姿を隠して、しかしパンを柔らかく豊かに作り上げてゆくのです。
「神の国はそのようにして、あなたがたの間に育つのだ」と、主イエスは教えてくださいました。神を真剣に拝もうとする礼拝から、そんなふうに神の国が私たちの間に育って行きます。
しかしそれは、トントン拍子に右肩上がりで進むとは限りません。主イエスの時代のパン種は、現在のドライイーストとは少し違っています。少量の小麦粉の中に酵母菌を育てたものであり、パン種はとても臭いが強かったことが知られています。40ℓもの粉にそれを混ぜて発酵させるとなると、当時の一部屋の家では家中にかなりの発酵臭が満ちたに違いありません。
しかし考えてみると、教会の成長にはそのようなところがあるように思います。人がどんどんと加われば、教会の中には人間臭い弱さや破れも見受けられるようになります。これは止むを得ないと思います。私たちが一人ひとり、生身を引きずって生きている人間である以上、教会が育っていく過程で醗酵臭が満ちる場合があることを覚悟しなければなりません。しかし、そういう過程を通って、パンはパンとして形作られてゆくのです。パンになりきってしまった時には、もうそこに醗酵臭はありません。
私たちは、教会に天使たちのような交わりを期待はできないように思います。けれども、様々な臭みを持って弱さを抱えている私たち一人ひとりが、この教会に招かれ、一つの群れとされ、主の御言に励まされ力づけられながら、次第に大きな木に育てられ、神への感謝と喜びも更に大きくされるのだということを憶えたいのです。
主イエスがサタンに勝利して一人の女性を神の許に導いてくださったように、そしてこの女性が背を伸ばして神を誉め讃える者とされたように、私たちもまた、それぞれに抱えている弱さを持ちながら、しかし、「神さまの御業が本当にわたしを支え、慰め勇気づけてくださる。わたしに生きる力を、今日与えてくださっている」ことを讃える者としてくださることを信じて、今日ここから新しく歩み出す者とされたいと願います。お祈りをささげましょう。 |