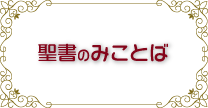 |
2025年10月 |
|||||
| 10月5日 | 10月12日 | 10月19日 | 10月26日 | |||
毎週日曜日の礼拝で語られる説教(聖書の説き明かし)の要旨をUPしています。 *聖書は日本聖書協会発刊「新共同訳聖書」を使用。 |
||||||
| ■「聖書のみことば一覧表」はこちら | ■音声でお聞きになる方は |
| 狭い戸口から | 2025年10月第3主日礼拝 10月19日 |
宍戸俊介牧師(文責/聴者) |
|
聖書/ルカによる福音書 第13章22〜30節 |
|
<22節>イエスは町や村を巡って教えながら、エルサレムへ向かって進んでおられた。<23節>すると、「主よ、救われる者は少ないのでしょうか」と言う人がいた。イエスは一同に言われた。<24節>「狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。<25節>家の主人が立ち上がって、戸を閉めてしまってからでは、あなたがたが外に立って戸をたたき、『御主人様、開けてください』と言っても、『お前たちがどこの者か知らない』という答えが返ってくるだけである。<26節>そのとき、あなたがたは、『御一緒に食べたり飲んだりしましたし、また、わたしたちの広場でお教えを受けたのです』と言いだすだろう。<27節>しかし主人は、『お前たちがどこの者か知らない。不義を行う者ども、皆わたしから立ち去れ』と言うだろう。<28節>あなたがたは、アブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。<29節>そして人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。<30節>そこでは、後の人で先になる者があり、先の人で後になる者もある。」 |
|
ただ今、ルカによる福音書13章22節から30節までをご一緒にお聞きしました。22節に「イエスは町や村を巡って教えながら、エルサレムへ向かって進んでおられた」とあります。この時、主イエスの姿に出会っていた弟子たちや群衆は、主イエスが神の事柄について教えてくださる方だという風にだけ思っていたことでしょう。あるいは、主イエスが病気の人や体の不自由な人、悪霊に捕われてしまっている人々を癒される癒しの業が行われることを期待しながら、主イエスのなさることを見守っていた人もいたかもしれません。しかし主イエス御自身は、人々を教えることや癒すことよりも、もっと重大な業を行うためにエルサレムに向かって進んでおられました。このことを、当時の人々はどれほど分かっていたことでしょうか。 ところで、この日、そんな風に道を進んでおられた主イエスに向かって質問した人がいました。23節に「すると、『主よ、救われる者は少ないのでしょうか』と言う人がいた」とあります。この人が主イエスの弟子の一人だったのか、それとも行きずりの人であったのかは分かりません。しかしまた、このように尋ねた人が、「救われる者」という言葉で実際にどういう人間の状態を思い浮かべていたのかもはっきりとは分かりません。しかし主イエスは、この質問の中に少し気になる点がおありだったようです。それは、質問したこの人のありように限ったことではなく、多くの人の心に兆す思いなのかも知れません。主イエスはこの人に対して、というよりも、その場に居合わせた人全体に向かって、「狭い戸口から入るように」と答えられました。24節に「『狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ』」とあります。 では、主イエスがおっしゃったこの言葉、「狭い戸口」とは一体何を伝えようとしているのでしょうか。「狭い戸口から入るように努めなさい」という話は、マタイによる福音書7章13節に述べられている「狭い門から入りなさい」という言葉と混同して受け取られがちです。マタイによる福音書で「狭い門から入りなさい」と言われている言葉がルカによる福音書では「狭い戸口から入るように」と教えられているのは、言葉は違っても同じ内容が語られているのだろうと考える人は多くいます。しかし、実際にこの2つの言葉を読み比べてみると、どうも違った事柄であるようなのです。というのも、マタイに出てくる「狭い門から入りなさい」という教えは、「滅びに至る広い門と対比して、広い門から入ろうとする人は多いけれども、命に至る挟い門を見い出すは人は少ないのだ」と教えられています。マタイは、広い門ではなくて狭い門から入るように教えています。しかしルカによる福音書では、狭い戸口は広い戸口と対比されている訳ではありません。むしろ「この戸口は狭いけれども、ここから入るように努めなさい」と主イエスはおっしゃいます。「努めなさい」というのは「懸命に努力を続けなさい」という意味ですが、こんな風に主イエスが何かを努力するように命じる箇所というのは、福音書全体を見渡しても、そう多くありません。マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書は、お互いに語られている内容に似たところがあるので共観福音書と呼ばれますが、共観福音書の中ではこの「努めなさい」という言葉は、ここにしか出てきません。ヨハネによる福音書には1回だけ出てきますが、そこでは「戦う」と訳されています。ですから、「狭い戸口から入るように戦いなさい」あるいは「奮闘しなさい」と、主イエスはここで命じておられるのです。 しかし、「狭い戸口から入るように奮闘する」というのは、実際のところ、どういうあり方をすることなのでしょうか。またどうして奮闘しなくてはならないのでしょうか。主イエスは続けておっしゃいます。「言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ」、これは一体何のことを言っているのでしょうか。そこに入りたいと思っても入れない人が多いのだと言われている「救いに至る狭い戸口」とは、何のことなのでしょうか。これは、主イエス御自身のことを言い表しているのではないでしょうか。主イエスは今、エルサレムへ向かって進んでおられます。そこでやがて十字架にお掛かりになります。それは、私たちと無関係に起こる出来事ではありません。私たちがそれを認めるか認めないかは別として、主イエス御自身は私たちの人間の罪をすべて御自身の側に引き受けて十字架に掛けられ、苦しめられ散々に痛めつけられて最後にお亡くなりになります。そういう仕方で私たちのための救いの御業を果たされる、主イエスはそういう救い主なのです。 この招きの言葉が聞こえているのに、この戸口から入ることをためらっていると、どうなるでしょうか。主イエスは何度でもこの言葉を語りかけてくださいますが、しかしいつしか私たちは、その招きにすっかり慣れっこになってしまう時が来るかもしれません。そして、主イエスの言葉を耳にしても、それがもはや自分への招きだとは聞こえなくなる時が来てしまうかもしれません。 今私たちの前に開かれている狭い戸口、即ち「主イエス・キリストが救い主として私たちの罪を清算してくださっていると信じ、それに相応しく生きなさい」という招きに従うことをためらっているうちに、呼びかけにすっかり慣れっこになり戸が閉じてしまうと、27節のような言葉が、私たちにも語りかけられることになるかもしれないのです。即ち「お前たちがどこの者か知らない。不義を行う者ども、皆わたしから立ち去れ」という、大変に厳しい言葉を聞かされてしまうことが起こるかも知れないのです。 今日の箇所で主イエスが告げておられるのは、決して、狭い道を行く少数の者と広い道を行くより多くの者たちがいるというような一般的な教えではありません。そうではなくて、主イエスの十字架の死と復活によって、「あなたには、今、主の苦しみによって罪の清算がつけられた赦しが確かに与えられている。これは、このことを信じる以外、他の方法では決してもたらされることはない。そういう意味で『狭い戸口』があなたの前に開かれているのだ」と、主イエスは語りかけておられるのです。 |
|
