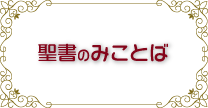ただ今、ルカによる福音書10章8節から16節までをご一緒にお聞きしました。
8節に「どこかの町に入り、迎え入れられたら、出される物を食べなさい」とあります。主イエスが復活後に行こうとして おられる先の町や村に72人の弟子たちをお遣わしになりました。その72人にお与えになった指示、あるいは遣わされてゆく上での心構えについて、主イエスが教えておられます。遣わされて行った先の町に迎え入れてもらったなら、「そこで出された物を食べて生活するように」と主イエスはおっしゃいます。食べ物についての指示を、主イエスは殊の他大事なことと思っておられたようです。そのことは直前の7節にも、よく似たことが指示されていることから分かります。7節では「その家に泊まって、そこで出される物を食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな」とあります。7節では、72人の弟子たちが遣わされた先に出向いて行って、どこかの家に迎え入れられたなら、その町で働く間は、身を寄せる家を変えてはならないことが教えられていました。これは、同じ町の中で仮に弟子が出入りする家を変えたならば、最初に世話になった家よりも、後から世話になった家の方が待遇が良く、おいしい物を食べさせてくれるのだということになって、同じ町の人同士で妬み合いや諍いが起こりかねないためだと言われています。人間的には、おいしい物を食べさせてくれたり待遇良くしてくれる方へ下宿場所を変えたいという思いが兆すのは止むを得ないことですが、しかし、主イエスの弟子たちは、そのようにこの世的な考え方に陥ってはならないことが戒められていました。
そして8節では、改めて、どこかの町で受け入れてもらえたなら、そこで出された物を食べるようにということが念を押すように語られています。どうしてでしょうか。
このような主イエスの指示を聞くと、どうしても思い起こされる出来事があります。それは、弟子のペトロがヤッファの町にいた時に見せられた幻の出来事です。使徒言行録10章10節から16節に、「彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになり、天が開き、大きな布のような入れ物が、四隅でつるされて、地上に下りて来るのを見た。その中には、あらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていた。そして、『ペトロよ、身を起こし、屠って食べなさい』と言う声がした。しかし、ペトロは言った。『主よ、とんでもないことです。清くない物、汚れた物は何一つ食べたことがありません。』すると、また声が聞こえてきた。『神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない。』こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた」とあります。このペトロの姿勢が表しているように、ユダヤの人たちには食事についてある種の潔癖さがあり、うるさいところがありました。しかし主イエスは、72人の弟子たちに教えるのです。「何であれ、あなたがたが食べるように提供される食事は、あなたがたの働きの報酬として神さまがあなたに与えてくださった物である。だからあなたは、出される物を感謝して食べるのが良いことだ」と教えてくださいました。「神さまが清めてお与えくださる物を、あなたが勝手に清くないと言ってはならない」、主イエスが遣わしてくださって出掛けて行く僕たちにとっては、行き先で出会う一つ一つの事柄すべてが清められているということを、この食事の言葉は教えてくれています。
こういう言葉を聖書から聞かされると、私たちは、礼拝から遣わされて一巡りの時を過ごすように送り出されてゆく私たち自身の生活の姿を、この72人の弟子たちに重ね合わせて考えることができるのではないでしょうか。礼拝が終わり、主の祝福を頂いて、銘々の生活へと遣わされて行く時、一巡りの生活の中で、どのような出来事が行く手に待ち受けているかを私たちは知りませんけれども、たとえ何が起ころうとも、神は私たちのために予め清い食卓を整えてくださり、私たちを養い、持ち運んでくださるということを信じたいのです。神が与えてくださる糧に養われながら、私たちは、主から遣わされた僕としてのありようを励まされ、力を頂いて、それぞれの生活に仕える者たちとされたいと願います。
さてそのように、私たちの生活は「主によって遣わされてゆく生活」なのですが、それは現実的にはどのような生活となるのでしょうか。具体的な過ごし方はそれぞれであるとしても、私たちがどこでどのように生活するとしても、私たちの生活には一つの約束が与えられているのです。それは、「これからあなたが行こうとしているところに、わたしも行こうとしている」という、主イエスの約束です。私たちがここから遣わされていく時には、主イエスが私たちのもとをきっと訪れて来てくださり、慰めと霊の力を与え、また、主によって癒される、そういう生活が与えられるのではないでしょうか。
72人の弟子たちに主イエスはおっしゃいました。9節に「その町の病人をいやし、また、『神の国はあなたがたに近づいた』と言いなさい」とあります。主から遣わされた人々は、共に生活する人々を癒し、また神の国の訪れを告げ知らせる働きをする者たちとされます。しかしこういう言葉を聞くと、また考えてしまいます。出会う人々を癒したり、「神の国」の訪れを告げ知らせるというのは、実際のところ、どうすることなのでしょうか。
私たちは地上の生活の中で、深い悩みの中にある知人がいたり、苦しみや戦いの中に置かれている友人の姿を見ることもありますが、そういう人に出会ったら、お祈りをして、病気や抱えている問題を解決してあげなさいということなのでしょうか。しかし、果たしてそんなことが私たちにできるのでしょうか。また、「神の国が近づいた」と、神の国の訪れを告げ知らせると言っても、その「神の国」とは一体何なのでしょうか。実際のところ、私たちには、誰かを癒す力も、また神の国の訪れを誰かに教えてあげる知恵も持ち合わせていないのではないでしょうか。
72人の弟子たちは、主イエスからこのように求められて遣わされて行ったのですが、果たして主イエスから求められたことを為せたのでしょうか。今日の箇所のすぐ次の10章17節を読むと、弟子たちの言葉が語られています。「七十二人は喜んで帰って来て、こう言った。『主よ、お名前を使うと、悪霊さえもわたしたちに屈服します。』」とあります。遣わされた 72人の弟子たちは、遣わされた先で困惑することなく、喜んで帰って来たと言われています。主イエスの名前を使うと、悪霊さえもが72人に屈服したと語っています。一体、何が起こったのでしょうか。
17節の言葉を読むと、私たちは誤解して、弟子たちが魔法の合い言葉のように主イエスのお名前を出すと悪霊が立ち所に言うことをきいたのだと感じるかもしれません。つまり、病気の人や悪霊に取り憑かれた人たちに向かって、「主イエスの名によって命じる。この人から出て行きなさい」と言うと即座に出て行ったと思うかもしれません。けれども、実際に主イエスの名前はそのように魔法の言葉のように使われるのでしょうか。そうではないと思います。そうではなくて、主イエスのお名前を使うというのは、悪霊や病気や困難な事柄に出遭って途方に暮れるとき、そんな自分たちの許に「どうか、主イエスがやって来てくださいますように」と、真剣にまた粘り強く祈ったということではないでしょうか。72人の弟子たちが遣わされて行った先というのは、そこに主イエスが後から出掛けて行くと約束してくださっている場所です。弟子たちは、そういう約束が与えられていることを覚えて、困難や苦しみに出会う度に、「このところにも主イエスがやって来てくださいますように」と祈り、待ち望みつつ、困難な状況の下を何とか持ち堪え、そこをくぐるようにして歩んで行ったのではないでしょうか。
すべてが自分たちの思い通りになったということではないかもしれません。難しいこと、解決できないことが残っているかもしれないけれど、しかしそれでも、「主イエスは、そんなわたしの許に来てくださって、今日のこの生活の中でわたしを支え、持ち運んでくださった」と思い、72人はそういう主イエスを慕い、喜んで主イエスの許に戻って来たのではないでしょうか。「本当におっしゃった通りでした。あなたから遣わされた生活にはいろいろなことがありましたが、しかしわたしはあなたの保護のもとに生きることが許されました」と言って、喜ぶことができたのです。
また、「神の国の訪れを誰かに告げ知らせる」ということも、はっきり言ってしまえば、それは、「主イエスが今、私たちと共にいてくださることを信じる」という仕方で伝える他ないことです。なぜなら、「神の国」というのは、どこかにある場所ではないからです。「神の国」という言葉は、英語の聖書では必ず「kingdom」と記されます。「kingdom of God」で「神の国」を表します。「kingdom」という言葉の中に、「king」即ち「王」という言葉が入っていますが、「神の国」というのは、「神さまを真の王として、神さまに従う生活」のことなのです。
ですから主イエスは、ファリサイ派の人から神の国について尋ねられた時、「それは領土を持つ国のように、肉眼で見えるものではない」とお答えになりました。ルカによる福音書17章20節21節に、「ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。『神の国は、見える形では来ない。「ここにある」「あそこにある」と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ。』」とあります。
「神の国」というのは、神を自分の本当の王とし、神に従順に従って生きる生活のことなのですが、そういうあり方のできる人間がどこかにいるかと言えば、どこにもいません。私たちは、神を王とするのではなくて、自分自身を人生の主人公に据えて暴君のように振る舞うようなところがあります。その点で例外はありません。私たちは誰もが、特別にエゴイストだと言われなくても、当たり前に自己中心的に生きてしまいます。従って主イエスがおっしゃるように、神の国は見える形では来ないのです。ただ一人、主イエスだけが、飼い葉桶から十字架に至るまで、まっすぐに神に従う生き方をなさいました。そして、その主イエスから「わたしに従って来なさい」と招かれて、私たちはキリスト者とされています。神の国が近づいたとか、やって来ているというのは、「ここにある」とか「あそこにある」という場所を指すのではなくて、主イエスがまさに私たちの許を訪れてくださり、「あなたと共に歩んであげよう。私についてきなさい」と言ってくださる事実の中にあるのです。
私たちは、自分一人で神の国を現すことはできませんけれども、しかし主イエスが私たちを招いてくださって、私たちが喜んで従う時に、その一瞬に神の国の人らしい香りを発するということはあり得るのです。神の国というのは、そういう仕方で、「あなたたちの間にある」と、主イエスは教えてくださっているのです。私たちは、放っておけば自分中心な在り方にいつでも陥ってしまいます。けれども主イエスが「わたしに従って来なさい。共に歩んであげよう。あなたを罪から解き放って、神さまに赦された者として人生を生きる者としてあげよう」と語りかけてくださるので、私たちは罪の重荷から解き放たれて、神の国に生きる者とされ、喜んで生活することができる者とされているのです。
ですから、遣わされて行った72人の弟子たちが「神の国を宣べ伝えた」という時には、遣わされた生活の中で、「今日ここに、どうか主イエスが来てくださり、わたしに伴ってください」と祈り、自分なりに主イエスに従って喜んで歩んでいくところで、「神の国が確かに来ている」ことを告げ知らせることになるのです。神の国の訪れというのは、私たちが上手に説明することで分かってもらうのではなくて、私たちが毎日、主イエスに伴われて、罪を赦され、神の者とされていることを信じて生きてゆく、その生活を通して周りの人たちに伝えられてゆくものなのです。
72人の弟子たちは、主イエスが「これからわたしが行こうとしている場所に、あなたがたを遣わす」という主のお言葉を信じて、病や悩みや困難の中にある人に出会うという生活を過ごしました。そして、そういう生活を過ごしているところに、主イエスが約束のとおりにやって来てくださって、一人一人をそれぞれの生活の中で相応しい歩みへと導いてくださったのです。
そのような生活の中に主イエスが来てくださり、神の力が働いて、元々は自分中心に物事を考えるのが当たり前だった私たちが、神に仕え、また隣人を思い遣って生きる新しい生活の形を与えられています。そしてそのことを喜んで生きるようにされるのです。72人の弟子たちは、そういう生活を経験して、喜びながら主イエスのもとに戻って来たのでした。つまり、主イエスが共に歩んでくださることを信じて生きるときには、悪霊からも自由にされ、一巡りの日々を神の保護のもとに生きることが許されたのだということを経験し、感謝し喜び、主イエスに報告したのでした。
「神の国」、「神の憐れみと慈しみに満ちた御支配」は、そのように主イエス・キリストが私たちの許を訪れてくださることを通して、また、主に信頼して生きる信仰生活を通して、私たちの間にもたらされます。ですから、誰かを癒したり、神の国の訪れを伝えるというのは、何か特別なやり方があるのではなくて、「主イエスが今日ここに、このわたしの生きている生活のただ中にやって来て、共に住んでくださいますように」と祈り、また共にいてくださる主イエスに信頼して生きることによって、果たされてゆくのです。
今日の箇所の最後のところ、16節で主イエスは「あなたがたに耳を傾ける者は、わたしに耳を傾け、あなたがたを拒む者は、わたしを拒むのである。わたしを拒む者は、わたしを遣わされた方を拒むのである」と、弟子たちに教えられました。これは、「神の国」が「主イエスが共にいてくださる」ということに他ならないことを教えている言葉でしょう。「神の国がやって来ている。今あなたはその前にいる」と教える言葉、私たちに語りかけられている言葉は、主イエス御自身の言葉なのです。
私たちは礼拝をささげる度に、主イエスが私たちの生活に伴ってくださることを、御言を通して知らされます。それはまさに、主イエス御自身がここに来てくださって、私たちに語りかけてくださっている言葉なのです。
主イエス・キリストが、「今日、あなたと共に歩んであげよう」と、あなたに語ってくださっています。私たちは銘々に、その語りかけを聞いて、主に従い、御国の民の一人として、ここから歩み出したいと願うのです。お祈りをささげましょう。 |