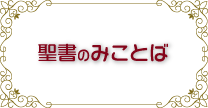 |
2025年9月 |
|||||
| 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 | 9月28日 | |||
毎週日曜日の礼拝で語られる説教(聖書の説き明かし)の要旨をUPしています。 *聖書は日本聖書協会発刊「新共同訳聖書」を使用。 |
||||||
| ■「聖書のみことば一覧表」はこちら | ■音声でお聞きになる方は |
| 復活の主と出会う | 2025年9月第3主日礼拝 9月21日 |
宍戸尚子教師(文責/聴者) |
|
聖書/マタイによる福音書 第28章1〜15節 |
|
<1節>さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが、墓を見に行った。<2節>すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から降って近寄り、石をわきへ転がし、その上に座ったのである。<3節>その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。<4節>番兵たちは、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。<5節>天使は婦人たちに言った。「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、<6節>あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。<7節>それから、急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あの方は死者の中から復活された。そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。』確かに、あなたがたに伝えました。」<8節>婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。<9節>すると、イエスが行く手に立っていて、「おはよう」と言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。<10節>イエスは言われた。「恐れることはない。行って、わたしの兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこでわたしに会うことになる。」<11節>婦人たちが行き着かないうちに、数人の番兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。<12節>そこで、祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて、<13節>言った。「『弟子たちが夜中にやって来て、我々の寝ている間に死体を盗んで行った』と言いなさい。<14節>もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなたがたには心配をかけないようにしよう。」<15節>兵士たちは金を受け取って、教えられたとおりにした。この話は、今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。 |
|
ただいま、マタイによる福音書28章1節から15節をご一緒にお聞きしました。 教会の基と言える天使の言葉は、どのような状況で語られたのでしょうか。この天使の言葉を最初に聞いたのは婦人たちだったと、マタイは記します。1節に「さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが、墓を見に行った」とあります。マグダラのマリアともう1人のマリアは、27章61節にも登場しています。「マグダラのマリアともう1人のマリアはそこに座り、墓の方を向いて座っていた」。使徒と呼ばれた12人の弟子たちは逃げてしまっている中で、ユダヤ教の議会サンヘドリンの委員のアリマタヤのヨセフが登場しました。この人は十字架上で死なれた主イエスの御遺体を引き取って、綺麗な亜麻布に包んで、自分の墓、新しい墓に納めた人です。その一連の作業を2人のマリアは見ていました。墓の方を向いて座っていました。主イエスの御体が確かに墓に葬られ納められ、大きな石で閉じられたのを見ていたのでした。そして、週の初めの日の明け方、2人は墓を見にやってきます。十字架で死なれた主の墓を見るためです。主の死を見るため、主がもう生きておられないことを心に刻もうとするためだったかもしれません。 一方、その神の世界を見せられて恐ろしさのあまり震え上がる人たちもいます。4節です。「番兵たちは、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった」。番兵たちが墓を見張るために派遣されたことは、マタイだけが描いている内容です。そしてその番兵たちが死人のようになったと語られます。光り輝く天の使いの威厳を前にして恐れのために震え上がる彼らの姿。マタイは光の世界、命の世界が死の世界を震え上がらせ、飲み込み勝利する様子を対比するように描き出しています。そのことは、3節4節に「ように」という言葉が3回続けて使われることからも分かります。「主の天使は稲妻のように輝き、雪のように白い衣の姿をしている一方、番兵たちは死人のようになった」。稲妻のような輝きと雪のような白さを持って神の威厳に満ちている天使の姿と、死人のような姿の番兵たち。マタイはこの時起こった出来事が命と死の戦いであり、その戦いは、命が、神の世界が勝利を収めたのだと語ろうとしています。 主の天使の姿と、その行動を震え上がって恐れた番兵たちがいる一方、女性たちはどうだったのでしょうか。彼女たちも恐れてはいたようです。8節に「婦人たちは恐れながら」とあるからです。ただ番兵たちと婦人たちの大きな違いは、彼女たちがこの後、天使の語りかける言葉を聞いたことです。そして、その言葉を信じて従ったことです。天使は言いました。「恐れることはない。十字架につけられたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさったのだ」。「恐れることはない」、元の言葉は「あなたがたは恐れるな」となっています。「恐れてはならない。恐れる必要はない。なぜなら」と続いています。なぜ恐れなくて良いのか、理由は2つあります。 それでは、よみがえられた主はどこに行かれたのでしょうか。今どこにおられるのでしょうか。天使は話を続けます。7節です。「それから、急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あの方は死者の中から復活された。そして、あなたがたより先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。』確かに、あなたがたに伝えました」。マグダラのマリアともう1人のマリア。2人は天使から主のよみがえりを告げられた後、さらにそれを弟子たちに伝える者となるようにと命じられています。ここには、「彼の弟子たちに」と、弟子たちが主イエスの弟子であることが、ことさらに強調されています。弟子たちは、今は姿を隠しています。十字架にお掛かりになった主を見捨てる形で主を知らないと言ってしまい、散り散りになっています。「けれども、彼らも主の弟子なのだ。その弟子たち、主に従って行くことができなかった弟子たちに告げなさい。『あなたの先生、主なる方は死者の中から復活された。そしてあなたより先に、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。そこでお会いできる。主はあなたたちをガリラヤでお待ちになっている。ガリラヤへ行くように。そこでもう一度、よみがえられた主にお会いするのだ』」。主から離れてしまった弟子たちは、それでもなお呼びかけられ、「あなたはわたしの弟子だ。ガリラヤへ」と語りかけられています。 女性たちは天使の言葉を聞いたとき、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行ったと語られます。救い主の誕生を知らされた羊飼いたちが「さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか」と急いで出かけて行った出来事のようです。あの時の羊飼いたちも、主の天使から「恐れるな」と呼びかけられていました。「なぜなら、神全体に与えられる大きな喜び、あなたがたのための救い主がお生まれになったからだ」。今回もそうです。「救い主があなたがたと共に生きてくださる。主イエスがあなたと共におられる。だから恐れなくて良い」。女性たちは確かに恐れていました。けれども同時に、天使の言葉を聞いて大いに喜んでもいます。そしてこの知らせを弟子たちに急いで知らせようと走っていきます。 女性たちが走っていると、よみがえられた主はおいでになったと9節に記されます。「すると、イエスが行く手に立っていて、『おはよう』と言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した」。よみがえられた主が女性たちの行く手に立っていて出迎えます。「見よ、主イエスは彼女たちを出迎えた」と記されています。そして「おはよう」とおっしゃいました。口語訳聖書では「平安あれ」、文語の聖書では「やすかれ」となっています。一方、「おはよう、平安あれ」と訳される言葉は、「喜ぶ」という言葉の動詞で、「喜べ」と直訳して「喜びなさい。喜べ」と主が言われたと訳す人もいます。いずれにしても、よみがえられた主は女性たちに挨拶をしてくださり、喜びの時を与えてくださいました。女性たちは主の足を抱きしめ、その前にひれ伏したとあります。「ひれ伏す」というのは、「礼拝すること」を表しています。よみがえられた主が神その方であることを知って、彼女たちは主イエスを礼拝したのでした。「主が復活され、今も生きておられる」、この信仰によって礼拝がささげられます。私たちも主の足にすがりつくようにして、主の御言葉を与えられ、礼拝をおささげします。ここでも女性たちの姿は、私たちの礼拝の姿を示しています。 主イエスはさらに語りかけます。10節に「イエスは言われた。『恐れることはない。行って、わたしの兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこでわたしに会うことになる』」とあります。天使が彼女たちに伝えた同じ言葉を、主も語られます。「恐れることはない。恐れるな。あなたがたは恐れなくて良い。行け、わたしの兄弟たちに告げよ」となっています。ここで弟子たちは、「わたしの兄弟たち」と、主から呼びかけられています。天使は、つまずき裏切った弟子たちを、なお主イエスの弟子と呼んでいました。けれどもここでは、主イエス御自身が彼らを「わたしの兄弟たち」と呼んでくださっています。「あなたたちはわたしの兄弟だ」。主イエスを裏切り、信仰において挫折し、弟子となることができなくなっている人たちでした。けれども、その弟子たちを主イエスは赦して、「わたしの兄弟」と呼んでくださっています。 さて、11節から15節までに記されたエピソードは、27章62節から66節の内容とつながっています。27章の終わりのところでは、祭司長たちとファリサイ派の人々が、弟子たちが主イエスの御遺体を盗み出して「復活した」と言い広めること、それによって人々が惑わされることを恐れていました。それで彼らは墓に番兵を置き、墓石に封印します。ところが番兵たちは、主の天使が地震を起こし、主イエスがよみがえられた出来事に出遭います。番兵たちが天使の様子に恐れて死人のようになったとき、何を見、何を聞き、どうやってエルサレムの都に戻ったのかは記されていません。けれども、とにかく彼らはこの出来事をすべて祭司長たちに報告したのでした。つまり自分たちは墓の番をしていたが、今その墓は空であり、納められていた遺体はもはやないということです。これを受けて、祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与え、そして命じます。「『弟子たちが遺体を盗んで行った』と言いなさい」。「兵士たちは金を受け取って、教えられた通りにした」。ここには、よみがえりの真実を知る機会を与えられながら、それを否定し続け嘘を作り出して言いふらしていく、そのことに躍起になる人々の姿を見ることができます。けれども、このような裏工作を持ってしても、主イエスのよみがえりの事実は曲げられることはありませんでした。そればかりか、この出来事が世界を変えることになりました。 最初の教会はこういう中で主イエスの復活のメッセージを伝えていったことが分かります。けれども、これは今の時代も同じことです。復活に対する疑いと不信の心は、世界中に広まっています。そして私たち自身の中にも、こうした疑いの心が同じように存在しています。 |
|
