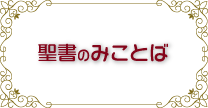ただ今、ルカによる福音書10章38節から42節までを、ご一緒にお聞きしました。38節に「一行が歩いて行くうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女が、イエスを家に迎え入れた」とあります。先週の礼拝では10章21節から24節をお聞きしました。順番通りであれば今日はその次の25節から37節の箇所になる筈ですが、その箇所は、「善いサマリア人」のお話で2022年1月に宍戸達教師が既に説き明かしましたので、今日はその先の「マルタとマリアの家に主イエスが立ち寄った時の出来事」を聞くことにしました。
38節には、主イエスが「ある村にお入りになった」とありますが、この村がどこの村であったかは伏せられた形で記されています。けれどもこの村は「ベタニア」という村で、エルサレムのすぐ前にある村です。主イエスがエルサレムに向かって行った長い旅行の様子を、もしもその旅の日程に従って書き記すとしたら、このベタニアのマルタの家に入った話はずっと後の方に記されるはずなのですが、ルカは、わざとそれを旅の始めの方に持ってきています。どうしてルカは、旅の初めのところにこの話を持ってきたのでしょうか。おそらく理由があるに違いないのです。その理由とは一体何でしょうか。
今日飛ばした25節から37節では、一人の律法の専門家が主イエスを試そうとして、ある問いを主にぶつけていました。25節に「すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。『先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか』」とあります。「永遠の命とは何か。何をしたらそれを生きることができるのか」と、難問を主イエスにぶつけています。それに対して主イエスは、逆に、「日約聖書の律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」とお尋ねになりました。律法の専門家が2つの旧約聖書の箇所、申命記とレビ記の言葉を引用して答えたところ、主イエスは「正しい答えだ。それを実行しなさい」とおっしゃったのでした。律法の専門家は主イエスからこの難問についての知識を得たかった訳ではなく、誰もが十分な答えを出すことができない問いをぶつけて、途方に暮れる主イエスを見てやろうと思って質問したのですが、思いがけず主イエスが明解にお答えになったものですから、逆に質問した自分自身を弁解したい思いになって、「では、わたしの隣人とはだれですか」と更に重ねて質問しました。そして、それに対して主イエスがお答えになったのが、「善きサマリア人のたとえ話」です。
今日の記事の直前に語られている「善きサマリア人のたとえ話」を、私たちは、そのお話の内容の方に引き込まれてしまって、「隣人というのは誰がその隣人に当たるかと考えて決めるようなものではなくて、私たちが自分から困っている人たちや難儀している人たちの隣人になることこそが大事なのだ」と気づかされて、話が分かったように感じるのです。けれども、元々あの話は、律法の専門家がまず答えた「隣人を自分のように愛しなさい」というレビ記の言葉について、重ねて質問した「では、わたしの隣人とはだれですか」という問いに対する答えとして述べられたものだったのです。
隣人に対するありようについては、「善きサマリア人の話」として説明されたのですが、律法の専門家が主イエスに、「永遠の命を受け継ぐために大切な事柄は何か」と問うたときに、主イエスに逆に問い返されて答えた事柄は、「隣人を愛しなさい」ということだけではありませんでした。もう一つ語っていたこと、それは申命記6章5節の引用で「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」という事柄でした。後の方のレビ記の言葉が「隣人に対するあり方」ですが、それはつまり人間同士の横の交わりがどうあるべきかを教える言葉です。それに対して、先に語られた申命記の言葉は、神に対する人間のあるべき姿を教える言葉です。
この「隣人に対する人間同士の横の関係のあるべき姿」、また「神と人間の縦の関係においてのあるべき姿」というのは、聖書の中で何度もくり返し語られる事柄でもあります。たとえば十戒の記された2枚の石の板の1枚目には、神との間柄、大切なありようが教えられ、2枚目の板には、人間同士の間で覚えておくべき大切なありようが教えられていました。主イエスが弟子たちに対して互いに愛し合うべきことを教えられた時にも、ただ単に「あなたたちは互いに愛し合わなくてはならない」とおっしゃったのではなくて、「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」と教えられました。人間同士の横の交わりとその間柄が健康なあるべき間柄であるためには、ただ「あなたは行って誰かの隣人になりなさい」と命じるだけでは不十分なのです。神との交わり、とりわけ神から愛され慈しまれている自分であることを知って、隣人もまた神に愛されているのだという理解がないならば、私たちは到底、自分の思いによって隣人を愛するなどということはできないでしょう。聖書の中からくり返し聞こえてくる、そうした神との縦の間柄と人間同士の横の間柄が本来のふさわしいものとして持ち運ばれることを教える言葉として、山梨英和学院のスクールモットーである「敬神、愛人、自修」という言葉もあります。神を敬うこと、そして隣人を愛して生きてゆくことの上に、自らを整えてゆく生き方があることを、あのスクールモットーは表わしています。更に言うならば、自修は「永遠の命を生きるために、どうあるべきか」という問いにつながっている言葉でもあります。自修は、ただ自分を治めて立派な人間になるということではなく、私たちが「永遠の命を生きるように」と招かれていることを知り、そういう神に愛されている者として生きることも含まれているのです。
前置きが少し長くなりましたが、聖書全体の中で、そんな風に、神との縦の結びつきに支えられて、隣人、即ち私たちお互い同士の横の間柄も整えられ、本来あるべき麗しい姿に持ち運ばれるのだと教えられているということを頭に置いて今日の箇所を聞きますと、どうして今日の箇所が、実際の日程をずらしてここに書き込まれているのかという理由が分かるのではないでしょうか。「善きサマリア人のたとえ話」は、隣人とのあるべき間柄を考えさせてくれる話ですが、それだけでは十分ではありません。神の御言によって教えられ、自分自身が御言の光に照らしていただくのでなければ、私たちの愛の業というものは、たちまち独り善がりな自己中心的なものとなってしまうでしょう。人間同士の間柄が本当に麗しい清潔な間柄として成り立ってゆくためには、私たち一人ひとりを深く愛し、罪から救い出して生かそうとしてくださる神がわたしの上にいてくださる、「神さまがいつも私たちに御言を語りかけ、生きるのだと言ってくださっている」ことを知ることが、どうしても外す訳にはいかない事柄となっているのです。そういう意味で、今日の箇所では「神さまとの間柄」を教えられていると言ってよいでしょう。ですから、「善きサマリア人の話」と「マルタとマリアの出来事」は、2つがセットの形で語られていると言えます。この福音書を著したルカという人は、一つの事柄を言うのに、一つの話で言い尽くそうとするのではなくて、2つ3つと話を重ねて色々な角度から光を当てて、いわば立体的に際立たせて説明するような書き方の癖を持っています。今日の箇所もその一つなのです。前の「善きサマリア人のたとえ」では隣人を愛する「愛人」という事柄を教え、今日の箇所では神に聴くこと、御言に耳を傾け受け入れることの大切さ、「敬神」という事柄を教えているのです。
今日の記事には、マルタとマリアという姉妹が登場します。この家には弟のラザロも暮らしていましたが、今日の箇所には現れません。もしかすると外出して不在だったのかも知れません。マルタとマリアの2人の姉妹は、血はつながっていますが性格は随分違います。姉のマルタは社交家で人をもてなすことを好み、よく気が回って働き者でした。これまでにも、多くの旅人を家に迎えて旅の疲れをときほぐし、そしてマルタ自身も、見知らぬ旅人との語らいの時を喜びとしてきたことでしょう。
けれどもこの日、マルタが家に迎えた客人は、これまで彼女がもてなしたどんな客人とも違っていました。彼女はまさにこの日、「主」と呼ばれるような方を客に迎えたのでした。仮にマルタがそのことの重大さに気づいていたならば、マルタは息を飲んで心臓が止まってしまったかも知れません。しかしここを読みますと、明らかにマルタの息づかいはいつもと同じようでした。かいがいしく心をこめて、いつものように、彼女は客あしらいに精を出します。勿論マルタは喜んで主イエスを迎えているのですから、その喜びの大きさ、思いの深さが、妹のマリアと比べて劣っている訳ではありません。2人の違いは思いの強さの違いではなくて、その思いを表す表わし方、考え方の違いであるにすぎません。
40節を見ますと、「マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていた」と言われ、また41節を見ますと、そういう生活の中でマルタが「多くのことに思い悩み、心を乱している」とも述べられています。この世を生きる中では、実際にマルタのように多くのことに思い悩み、心を乱さざるを得ない場合があるのではないでしょうか。自分では特にそうしたいと思わなくても、しかしどうしてもせわしい思いをしなくてはならないという場合もあります。私たちはそんな忙しい生活を過ごす中で、全部のことに気が回らなくなって失敗してしまうような時もあるかもしれません。
けれども、もしもそんな忙しさの陰で、家族や兄弟姉妹たちや大切にするべき存在に対して、反発や、いがみ合うような気持ちが芽生えてしまうとしたらどうでしょうか。元々悪気はなかったはずなのに、お互い同士の間が険悪になったり、心が荒んでしまったりするならば、一体どういうことになるでしょうか。主イエスは、マルタの心の中に生じた乱れを見逃しません。しかしそれを叱りもしません。「マルタよ、マルタよ」と優しく言葉をかけてくださいます。
一方、39節を見ますと、ここにもう一人、マリアという女性のことが述べられています。「彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足もとに座って、その話に聞き入っていた」。ここではマリアがまるで何もしないでいたかのように述べられています。しかし彼女は、決して怠け者で無能な人物というのではありません。他の場合であれば、マリアは自分のすべきことをしっかりと弁え、自分の仕事を果たしたに違いありません。普段がそうであればこそ、姉のマルタは、マリアが自分の忙しい立ち働きに加勢して手伝ってくれることを期待しました。ところが実際にはそうなっていないことに苛立ちを覚えているのです。
マリアはこの時、動きませんでした。どうしてでしょうか。マリアは今まさに、この瞬間が持っている意味の重大さを悟っていたからです。すなわち、自分たちの家を訪れて客人となった方がどのような方であるか、マリアは気づいていたのです。マリアは「主の足もとに座っていた」と言われています。今日の客人が他ならない「主」であると悟っていました。そしてそうであるからには、マリアは今、どうして他のことに気を散らしておれるでしょうか。どうして、食卓を整えたり食器のセットを並べたりすることに思いが向くでしょうか。目の前に主が来ておられる、そしてその主が自分に向かって語り始められるのです。
マリアはその足もとに座って、主イエスの口から語られる言葉を一言も聞き漏らすまいと努めました。マリアは、よりによって主が自分たちの家の戸を叩き、敷居をまたぎ、そして食卓についてくださったことを、深い驚きと感謝の思いをもって受け止めていたのです。
マリアはこの時、主の足もとに座りながら、「主」「客」が入れ替わっていることに気づいていました。確かにこの場所はマリアとマルタの家の居間ですが、今は自分たちが主を迎え入れているのではなくて、本当は主イエスの方が主であり、自分たちを招いてくださり、御言葉を語りかけてくださっているのです。その重大さに気づいたがために、マリアは主の足もとから決して離れませんでした。
しかしマリアが招かれて主の客となっている間、マルタの方は相変らず、自分がこの家の主人であって、客の接待の事柄で頭を一杯にしながらせわしく立ち働いています。この家には父母はおらず、マルタが家長だったようですが、彼女は家の中のことにすっかり気をとられ、その反面、「神の国の出来事」には気がついていないようです。「神の国が今、ここに訪れて来て、自分たちに呼びかけ戸口の扉を叩いている」ことが分かりません。そして、そういう姉の目には、妹のありようが何とも目に余る振舞いのように感じられます。即ち、「客がやって来ているのだから、家人は皆、自分と同じように立ち働かなくてはならない。それなのに妹のマリアはなすべきことを怠り、ほったらかしにしている」と思って、不満を募らせるのです。
そして遂に不満が破裂する時がきます。マルタは妹への不満を爆発させ、主イエスに対しても非難がましい言い方で語ります。40節に「マルタは、いろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。『主よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください』」とあります。マルタもここで「主」と呼びかけています。けれども同じように「主」という言葉を使いながら、マルタとマリアの間には、主に対して何という大きな受け止め方の違いがあることかと思わざるを得ません。マルタは客人として「主」と使っているだけなのです。しかしマリアは、「本当に主が来られた」と思って、主の足もとに座っています。
主イエスはマルタにお答えになりました。聖書を通してここの言葉を聞く限り、私たちには、主イエスがマルタを咎めてはおられるようには聞こえません。「マルタよ、マルタよ」と優しく呼びかけておられると聞こえます。
しかし、主イエスに言葉をかけられた当のマルタ自身には、この言葉はどう聞こえたでしょうか。何とも冷たく、また突き放されるような言葉に聞こえたかも知れません。マルタは喜びと好意をもって主イエスをもてなそうとしています。ところがそんなマルタにとって、自分のあり方が否定されたかのような言葉が主イエスの口から語られます。41節42節に「主はお答えになった。『マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない』」とあります。
ここに言われる「良い方」というのは、聖書の中では大変重要な表現です。そこでは、その人が相続すべき土地、あるいは相続財産のことが考えられる言葉だからです。例えばアベルは「良い方」を選びましたが、カインはそうではありませんでした。ヤコブは「良い方」を選びましたが、エサウはそうではありませんでした。「必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ」と主イエスはおっしゃいます。「マリアは今、良い方を選んでいる。それが彼女の相続する分として与えられている。それをあなたは取り上げてはならない」と言われるのです。「目の前に神が来ておられる。そして神の御言が自分に語りかけられている」、そのことを受け入れて神と結びつく間柄のことが、ここで「良い方」と言われている一つの事柄です。見出すに価するただ一粒の高価な真珠。あるいは、全財産と引き換えにしても是非掘り出して自分の所有とするに足る畑の中の宝。マリアはまさに、そういうお方との出会いを与えられ、そちらの方を選んでいます。それが主イエスの足もとに座って御言に聴き入るマリアの姿なのです。
「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない」という主イエスの言葉は、決してマルタを叱っている言葉ではありません。けれどもマルタからすれば、これは厳しい裁きのような言葉にも聞こえたかも知れません。彼女のこれまでの人生は、この言葉によって足元から崩れるかのようでした。まさしく主イエスのおっしゃったことは、これまでマルタが心がけてきた人生のありようを根底から突き崩すような言葉だったのです。マルタは、「あなたは今、良い方を選んでいない」と言われているようなものなのです。
けれども、このような裁きは、実はマルタにとっての祝福の言葉でもあるのです。主イエスのこの言葉は、当座はマルタを悲しませるでしょう。ですがそれは、マルタを拒否する言葉ではありません。主イエスは、たとえ厳しい処置をなさる場合であっても、救い主メシアであることをおやめにはなりません。主イエスのこの日の言葉は、マルタに対する招きの御声でもあるのです。マルタは今日のこの日の出来事を通して、彼女自身もまた「良い方」を選び取ることができる可能性を与えられているからです。マルタにも、マリアと同じように主の足もとに座り、そして自分自身にとって決して欠かすことのできない重大な宝として主の御言に耳を傾け、神との間柄を確かにされる道があるのです。
「どうしたってマルタには、マリアのようにこのチャンスを活かすことはできっこない」と言い切ることは、それこそ誰にもできません。主イエスが行こうとしてこの家を訪ね、敷居をまたいでくださっているからには、人間の側の鈍さや不従順が決定的なことになるとは誰にも言えないのです。早いか遅いか、それは私たちには分かりません。しかし、主イエスがかつてザアカイにおっしゃったのと同じように、「今日、救いがこの家に来た」という言葉が、マルタの家についても語られる日のあることを私たちは信じたいのです。
そしてここで起こっていることと同じことが、私たち自身の家についても語られる日が来ることを信じ、楽しみに待ち望みたいのです。
以前、主イエスが72人の弟子たちをお遣わしになった時に、それは後から主イエスが行こうとしている場所に72人を遣わしたのだと言われていました。私たちが今日ここから遣わされて行って、それぞれの生活に戻っていく時に、私たちが歩んで行く先の生活というのは、主イエスが必ずそこを訪れてくださるという約束が与えられている生活です。主イエスが来てくださり、私たちの出会う愛する者たちを憶えていてくださるのであれば、「この人は決して神を信じることなどあり得ない」などど、私たちは言ってはならないのです。
私たちは、憶える大切な人々も主イエスに呼びかけられ、そしてやがて主のものとされる幸いな日が来ることを信じるように招かれています。
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」という言葉は、ただ私たちが心の中で神を愛しているということではないのです。「神が今、わたしの上に働いてくださり、わたしの生活を用いようとしてくださっている。わたしは神さまと共に生きる者とされている」、そのことを信じて喜び、感謝をもって、ここから歩み出したいと願います。お祈りをささげましょう。 |