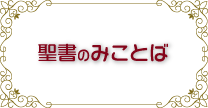ただ今、ヨハネによる福音書11章17節から27節までを、ご一緒にお聞きしました。その中の18節に「ベタニアはエルサレムに近く、十五スタディオンほどのところにあった」とあります。15スタディオンというのは3キロ足らずの道のりです。足が早い人なら1時間ちょっとで辿り着けそうな、それこそ目と鼻の先にエルサレムがあると言ってよいような場所にベタニアはあります。どうしてこのようなことがここに記されているのでしょうか。この福音書は、ここにエルサレムとベタニアの距離を書き記すことで、何を伝えようとしているのでしょうか。
この時、主イエスはエルサレムを目指して、そこで御自身がお掛かりになる十字架を見据えて旅を続けておられます。エルサレムまでの長かった旅が、今や最後の道にさしかかっていることを、この言葉は表しているのです。この最後の道のりは、文字通り、死の陰の谷を行くような道のりです。エルサレムには、主イエスを捕らえて命を奪おうとしている敵がうようよしています。そんな険しい危険の中にあって、主イエスは御自身の旅が死をもって終わるものでないことをはっきりと知っておられました。主が今歩んでおられる道は、確かに厳しく辛い死の出来事に直面することになります。しかし、死をもって終わるのではなくて、神の清らかな栄光と暖かな愛に満ちた永遠の命に復活するのです。その栄光と暖かな愛を、主イエスは旅の最終盤に示してくださいました。それがこのベタニアで起こったことです。今からエルサレムに向かう苦難の歩みが、しかし同時に、どんなに栄光に輝き、神の愛に満たされた歩みであるかということを、主イエスは御自身と大変親しい交わりを持っていた一つの家庭の上に現わしてくださいました。今日の記事が、エルサレムで実際に主イエスが十字架にお掛かりになって果たされる御業を指し示すような輝きに満ちた栄光の出来事であり、いわば主イエスがここまで辿って来られた旅の総決算のような出来事であることを、18節の言葉は物語っています。何も思わずに読んでしまうとつい読み飛ばしてしまいそうな言葉ですけれども、ここベタニアで起こった出来事が、たとえて言うと、エルサレムで果たされる主イエスの御業の露払いのような出来事であることを憶えたいのです。
何よりも主イエス御自身が、ここで起こる出来事の重大性を深く自覚しておられました。今日はベタニアのラザロの出来事のまん中に当たる箇所だけを聞きましたが、この出来事はかなり長く、12章11節まで続けて語られています。その長い記事のはじめ近くの11章4節で、主イエスは「この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである」とおっしゃっておられます。主イエスがこうおっしゃるのを聞いた時、弟子たちは、ラザロの病気が持ち直すと思ったに違いありません。けれども主イエスはこの時、ラザロが死の病を抱えていることを知っておられました。間もなくラザロが亡くなること、それによって2人の姉たちがすっかり打ちのめされ、死の力がこの家庭の上に重くのしかかるようになることを、主イエスは既にこの時点で御存知でした。しかし、それで終わりではないことを、主イエスはこの時、弟子たちに教えられたのです。
文字通り、死の陰の谷を行く道を辿ってエルサレムへと向かって行かれる主イエスがこれから果たそうとしておられる御業は、死との対決です。そして主イエスは、この対決を通して、死のただ中に新しい命をもたらしてくださいます。御自身の十字架の苦難と復活とによってです。そして主イエスは、ラザロの死とそれに続く一つながりの出来事を通して、死が最後の勝利者などでは決してなく、神こそが御心のままに自由に人間に命を与え生きる者としてくださる、そういう栄光に満ちた方であることを現してくださいました。「この病気は死で終わるものではない」とは、ラザロの病気がひとりでに持ち直すということではなくて、主イエスが人間の死に敢然と戦いを挑んでおられることを指し示しています。
人間はやがていずれは死にゆく者たちです。誰もが経験から、普通はそう考えます。けれども、その死すべき人間が神の御意思によって主イエスによって命を与えられ支えられて存在していることを知り、さらに神の愛が絶えず私たちに向けられ、私たちを生かしてくださることを私たち人間が信じるようになる時、そのところに神の栄光が現われるのです。
主イエスはラザロについて、「彼は死なない」とおっしゃったのではありません。「この病気は死で終わるものではない」、つまり、ラザロの死はきっと起こるに違いないけれども、それで終わるのではないとおっしゃいます。死とは終わりではなくて、言ってみれば、一つの通過点のようなものなのだと教えられます。これは、私たちの普通の生活感覚では、なかなか分かりにくいことだろうと思います。私たちの生活感覚から言うならば、私たちの命も日々の生活も、すべてこの地上で営まれます。私たちは、この地上の生活がすべてだと思って生活しています。そして私たちの肉体の死というのは、私たちの地上での時間が終わってこの世を去って行くということですから、すべてが終わってしまうと感じてしまうのです。そして、死の前には様々な予兆があります。よく見えていたはずの目がかすんできたり、耳が遠くなったり、足が前へ進まなくなったり、病気がちになったり、自分自身の体を以前より重たく感じるようになったりします。そうした不自由さを経験しながら、私たちは自分の世を去る日が次第に近づいて来ていることを思わされ、やがての日には、地上の生活を終える時がやって来て何もかもが終わるのだと考えたりするのです。
しかし実際には、私たちにはすべてのことが分かっている訳ではありません。むしろ知らないことの方がずっと多いのです。先日テレビの教育番組を見ていてとても驚いたのですが、南極大陸の厚い氷で覆われた下には、凍っていない真水の池が存在していて、その中に本当に小さなバクテリアたちが群れをなしてコロニーと呼ばれる森のようなものを形づくっていることを知らされました。南極の氷は非常に厚くて大陸の上に下の方まですべて凍りついているとばかり思っていましたが、地熱のために底の方は融かされて水になっている、しかもそこには無数のバクテリアが住んでいると教えられて本当に驚きました。しかしそれで感じたことは、この地上の自分の生きている場所についても、私たちは知らないこと、思いもよらないことがたくさんあるということです。神は望遠鏡で観測することはできませんが、それは神がいないことの証明にはなりません。そもそも聖書は、神は天地創造の時に時間と空間をお造りになった方で、神御自身は時空の外にいらっしゃる方だと語っています。私たちが知ることのできない遙か彼方に、神はおられます。
ところがその神が私たちに一人ひとりに御心を寄せてくださるのだと、聖書は語ります。命をお与えくださった主なる方として、私たちの日々の暮らしに御心を寄せてくださり、私たちが日毎に経験している苦しみも嘆きも悲しみもすべて御存知であり、また、私たちが小さく弱く臆病であるために常に堂々としておれず、しばしば失敗や間違いを犯しがちな罪人であることもよく知っておられるのです。そういう私たちを憶えてくださり、何とかして「神さまの保護のもとにある」ことを分からせ、「神さまが与えてくださった命である」ことを知らせようとしてくださるのです。永遠において「あなたはここで生きるのだ」と定めてくださるのです。「私たちの命とは、この地上で経験したり理解したりするよりも遥かに大きなものである」ことを、神は私たちに知らせようとしてくださるのです。何とかして、私たちが神の保護と御支配のもとに生きる者、永遠の命を生きる者となるように、神は道を拓こうとしてくださるのです。
神からすっかり切り離されて、私たちが自分一人で生き、そして死んでゆくということではなくて、たとえ肉体の死を迎える時にも、そこは一つの通るべき関所のようなものであって、道はそこで終わるのではなく、死を通って命はさらに持ち運ばれてゆきます。私たちは、「神の御支配と愛の下に、死を越えて存在するのだ」ということを知るようにと招かれているのです。
今日の箇所に記されている主イエスも、そのような神の御計画に従って行動しておられます。主イエスがベタニアのラザロの家を訪ねられた時、ラザロはお墓に葬られて既に日が経過していたことが17節に語られていました。ラザロが亡くなりすぐにお墓に葬られて4日が経っていたということですので、ラザロは4日前に亡くなったことを意味しています。主イエスの前にやって来た姉のマルタは、そのことを思って、しきりと残念がるのです。21節に「マルタはイエスに言った。『主よ、もしここにいてくださいましたら、わたしの兄弟は死ななかったでしょうに』」とあります。「どんなに深刻な病であっても、主イエスがもしここにいてくださったなら、弟は死ななかったのに」とマルタは思っています。そういう思いから、マルタは主イエスが訪ねてくださることも心の底から待ち望んでいました。もし主イエスが間に合っていれば、弟の病はきっと癒していただけたのに、しかし今となってはもう手遅れだという思いを、マルタは素直に主イエスに訴えています。
無論、マルタは弁えています。自分たちの都合よく主イエスや神が働いてくださる訳ではありません。神の御計画や主イエスの行動は、あくまでも神の御心に従い行われるのであって、たとえ人間の思いや願うこととは違うような結果になるとしても、そこにも深い配慮と導きがあると信じるべきことを、マルタは弁えていました。しかしそれにしてもマルタは、「もし弟の容態が悪化した時、主がそこにいてくださったならば」という思いを隠せず、率直に語ります。マリアも後のところでマルタと同じことを主イエスに言っていますから、マルタとマリアの間で、このことについて本当に残念だったという会話が交わされていたのかもしれません。この2人の姉たちは、主イエスを信頼していました。弟の病気について、もしイエスが間に合ってくださったなら、弟は助かっただろうと考えていたのでした。しかし、もはや手遅れです。死は2人にとって大切な弟を、永久に手の届かない死の世界へと運び去って行きました。少なくともマルタは、そう感じていました。
しかし、「主イエスは決して無力な方ではない」とマルタは思っています。弟の命は遂に助からず、そのため、今自分たちは死の支配の下ですっかり打ちのめされたようになっているけれども、しかし主イエスはこんな時にも、きっと自分たちにここから歩んでゆくべき道を指し示してくださる方だと信じています。
マルタたちは今、弟のことですっかり途方にくれてしまい、自分たちが神にどう祈ったらよいのか、何を祈るべきかが分からなくなっていますけれども、そんな自分たちに代わって、主イエスが2人を神に執り成してくださることを期待します。22節の言葉は、そういうマルタの期待が表れた言葉であると思います。「しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神はかなえてくださると、わたしは今でも承知しています」。これは決して、主イエスが神に願えば何でも叶えられるのだから、是非ラザロを生き返らせるように祈って欲しいという厚かましい願いではありません。そうではなくて、もっとずっとささやかな、弟の死の出来事に直面してどうしたらよいか分からずにいる自分たちのために、主イエスが何事かを神に祈ってくださいますようにという願いの言葉です。すっかり死の力に抑えつけられ押しひしがれて、息をするのもやっとになっている自分たちのために、どうか祈っていただきたいという願いを、マルタは言い表しているのです。ここにマルタの主に対する限りない信頼を聞き取ることができます。
しかし、こういうマルタの主への信頼、主を信じている姿は、限りなく主に信頼し頼ってはいるのですが、主イエスが今何のためにエルサレムに向かって進んでおられるのかということを理解できてはいない姿とも言えるでしょう。主イエスはこれからエルサレムに向かい、十字架にお掛かりになります。御自身の身を人間の罪の代償のいけにえとしてささげ、それによって人間を罪の赦しの下に置いて、人間を死から救い出そうとして道を進んでおられます。主イエスが十字架上に亡くなられることで、私たち人間の罪は清算されることになります。すると罪を清算していただいた人間たちは、罪から赦された者たちとして、再び神の愛と慈しみを受ける者たちとされるようになります。そのために主イエスは今、エルサレムの十字架を目指して進んでおられるのです。ですから主イエスは、他ならない罪と死を滅ぼすために道を進んでおられるのです。死を決して人間の主人であり最後の支配者としないために、今、道を進もうとしておられます。
ところがマルタは、死の力にすっかり押さえつけられて、自分では手も足も出ないし、それは主イエスも同じだろうと思っています。弟の死の事柄はもう仕方がないけれども、しかし、今地上を生きる自分たちのために、神に祈っていただきたいと願うのです。ところが、このようなマルタの姿が主イエスを大いに刺激します。ここで主イエスはマルタに、予想外の返事をなさいました。23節です。主イエスは、「あなたの兄弟は復活する」と言われました。主イエスは、御自身の御業とラザロを結びつけてくださるのです。主イエスが復活する、そのことの中に、ラザロを置いてくださろうとするのです。
けれども、この主イエスの言葉を私たちは一体どう聞いたらよいのでしょうか。少なくともマルタは、この時、主のおっしゃる意味が分かりませんでした。マルタは考えました。世界の歴史が完成される終わりの日に、歴史の中に生きた者たちは全員、その人の生きた生の意味を吟味するため、神によって復活させられることになっていると言われている、その復活のことを主イエスがおっしゃって、ある種の気休めを聞かせようとしてくださっていると思ったのです。
しかし主イエスがおっしゃったのは、遠い将来にラザロが復活することになっているということではありません。今、死の力にすっかり押さえつけられてしまっているマルタとマリアのために、死の力が最後の勝利者でないことを知らせるために、主イエスはラザロを復活させようとなさいます。「あなたの兄弟は復活する」とおっしゃった主イエスの言葉を正面から受け止められずにいるマルタのため、主イエスは更にはっきりしたことをおっしゃいます。25節26節です。「イエスは言われた。『わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。このことを信じるか』」。「わたしは復活である」「わたしは命である」と主イエスはおっしゃいます。主イエスはこうおっしゃって、マルタに信仰を求められるのです。しかし、一体誰がこのような主イエスのおっしゃりようを正面から受け止められるでしょうか。ここで主イエスが本当のことを包み隠さずにおっしゃればおっしゃる程、それを聞かされるマルタは当惑せずにいられません。彼女がようやく口にできたのは、主イエスへの限りない信頼の言葉でした。しかしながらこれは、主イエスが信じるように求められた事柄に対しての正面きっての返事にはなっていません。半ば口ごもりながら、マルタは答えます。27節です。「マルタは言った。『はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであるとわたしは信じております』」。
マルタは、主イエスが「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことはない。このことを信じるか」とお尋ねになった事柄に対しては正面から答えることができません。信じるようにと示された事柄についてではなく、彼女は、信じるようにとおっしゃってくださった方への信頼を口にします。
ヨハネによる福音書がこのようなやり取りを記してくれていることは、実は私たちにとっては真に幸いなことであろうと思います。主イエスがここで信じるように教えておられるのは死者の復活です。マルタはこの事柄について率直に答えることができません。主イエスのおっしゃることが、あまりにも突飛なことのように思えるからです。ですが、ここでマルタに語りかけられた言葉に対しては、今日ここに集まっている私たち一人ひとりも、やはりマルタと同じような反応しかできないのではないでしょうか。主イエスのおっしゃることは私たちの理解を超えているのです。「4日前に亡くなった弟が復活することになる」とか、「主イエスを信じる者は死んでも死なない」とか、「あるいは生きていて主を信じれば、その人は決して死なずに永遠に入るようになる」と聞かされても、私たちもまた、そういうことがよく分かって、「はい、信じます」などとは言えないのではないでしょうか。ここで主イエスが伝えようとしてくださる事柄は、私たちの理解を超えてしまうようなことなのです。私たちにとって精一杯できることがあるとすれば、聞かされた事柄についてはよく分からず、それについて信じるとは言えないとしても、復活という出来事を語りかけてくださる方は本当に信頼に足る方である、「わたしはこの方を信じます」ということまでしか言えないのではないでしょうか。マルタの返事は、私たちにとっては慰めであり、有難いことだと思います。私たちにとって「復活」は、やはり、私たちの理解の外にあるのです。
しかし死では終わらないことが、ここで明らかにされていきます。主イエスが実際にラザロを復活させるため、墓の入口を開こうとした時、マルタは、「主よ、四日もたっていますから、もうにおいます」と言葉をかけました。それに対して主イエスは、マルタの信仰を励ますようにおっしゃいます。40節です。「もし信じるなら、神の栄光が見られると、言っておいたではないか」。恐らくマルタは戸惑ったと思います。主イエスは、このことを一体、いつおっしゃったのでしょうか。これは実は、マルタに対してではなく、弟子たちに言われた言葉でした。「この病気は死で終わるものではない。神の栄光が現れるためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである」。主イエスは立ち戻って、こうおっしゃっています。まさに「ラザロの病気が死で終わるものではない。神の栄光がそこに現される。信じる者がその栄光を見るのだ」と、主イエスは言い表してくださいました。
ラザロはこの時、生き返りました。そのことをマルタとマリアは喜んだでしょう。けれども、生き返されたラザロは、その後永久に生きたわけではありません。しかし、この出来事を通して現されたことは、死がもはや最終的な事柄でも人間の支配者でもないことです。主イエスはこの時、ラザロを復活させることで、2人の姉たちに確かにこのことを示してくださったのです。たとえ地上に死という辛い出来事が絶えず起こり、死の力が人間の生きる力に勝っているように見えるとしても、永遠において私たち一人ひとりを憶えてくださっている神の愛は、死の力に勝って強いということを、主イエスはラザロの死とそれに続く出来事を通して知らせてくださいました。死んでしまった人間がどうしたら復活するのか、どのように復活させられるのかということについては、私たちには皆目分かりません。分かりませんから、それを信じますと軽々しく言うこともできません。けれども、「あなたがたは神さまに愛されている者で、命は神さまのものなのだ」と、そのように語りかけてくださる主イエスを信じてよいのだと、私たちは聖書を通して聞かされているのです。
このラザロの出来事は、ヨハネによる福音書では、主イエスがエルサレムにお入りになる直前のところに記されています。実際に救い主メシアとしての御業を果たされる、その直前の最後に記されている記事です。この記事は、十字架の御業のためにエルサレムに向かって行かれた主イエスの旅路全体における結びの記事であり、クライマックスであるとも言えるような、そういう意味合いでここに記されています。そしてこのことは、この福音書の結びのところでも、もう一度確認されていることでもあります。ヨハネによる福音書は全体で21章ありますが、元々は20章で一旦結ばれていたようです。20章の結び、31節には「これらのことが書かれたのは、あなたがたが、イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また、信じてイエスの名により命を受けるためである」とあります。この福音書が書かれた目的は、「イエスは神の子メシアであると信じるため」です。マルタは今日の箇所で「あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであるとわたしは信じております」と答えています。まさに、そういうところに導かれるために、この福音書は記されています。
私たちは、自分がどのように復活させられ命を受けるかは分かりません。けれども、主イエスがおっしゃることが本当だと信じる時に、「死が最後の勝利者ではなくなる。信じて、主の御名によって、あなたは命を生きることになる」ことを知らせるために、この福音書が記されているのだとヨハネは教えてくれています。主イエスを信じることによって、今を生きる命、それは病や老化など様々なことで脅かされている命ですが、「この命が神によって支えられていること」、「地上で過ぎ去ってしまうだけではなく、永遠に繋がっている命を生かされていること」を、私たちはこの福音書から知らされています。主イエスがまさにこのことをラザロの家庭の上に行ってくださったことを、今日の箇所から聞かされました。
そしてこのことは、私たちにもまた同じように、「信じてよいのだ」と主イエスが語ってくださり、そして信じるところで、「神の栄光に包まれて暖められ清らかに生きる、新しい者とされる」約束が与えられています。
私たちはこのことを信じて、ここから歩み出したいと願います。お祈りをささげましょう。 |