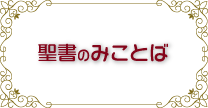 |
2025年4月 |
|||||
| 4月6日 | 4月13日 | 4月20日 | 4月27日 | |||
毎週日曜日の礼拝で語られる説教(聖書の説き明かし)の要旨をUPしています。 *聖書は日本聖書協会発刊「新共同訳聖書」を使用。 |
||||||
| ■「聖書のみことば一覧表」はこちら | ■音声でお聞きになる方は |
| 遣わされる民 | 2025年4月第4主日礼拝 4月27日 |
宍戸俊介牧師(文責/聴者) |
|
聖書/ルカによる福音書 第20章19〜23節 |
|
<19節>その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。<20節>そう言って、手とわき腹とをお見せになった。弟子たちは、主を見て喜んだ。<21節>イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」<22節>そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。<23節>だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」 |
|
ただ今、ヨハネによる福音書20章19節から23節までを、ご一緒にお聞きしました。19節に「その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、『あなたがたに平和があるように』と言われた」とあります。ここには、恐れと不安を感じて家の戸に鍵をかけ、自分たちだけであろうとする弟子たちの姿と、鍵が掛かっていた筈なのに、いつの間にか弟子たちの真ん中にやって来られ、「あなたがたに平和があるように」と御言葉をかけてくださる主イエスの姿が語られています。恐れと孤独の中にある弟子たちの姿と、祝福を与え平安の中に置いてくださる主イエスの姿が、ここに並んで述べられています。 弟子たちが不安を感じ恐れていた理由は、私たちにもある程度は理解できるように思います。つい数日前、彼らの仲間であったイスカリオテのユダの裏切りによって、彼らの目の前で主イエスが捕らえられ、むざむざと処刑されてしまいました。弟子たちには、まったくなす術がありませんでした。あの厳しい迫害の出来事が果たして主イエスお一人だけで終わるのか、それとも更なる追求の手が伸びてきて、今度は弟子たち自身が捕らえられ危害を被ることになるのか、彼らにはまったく見当がつきません。それで彼らは人目につかないように家の中に引きこもり、息を殺すようにして寄り集まっていたのでした。彼らが恐れたのは、人でした。 「平和を、あなたたちに」、この「平和」とは一体何でしょうか。ごく普通に考えて、私たちはこの平和を地上に成り立つ事柄として受け止めるのではないでしょうか。即ち、戦争や災害や飢饉や疫病がなく、また貧困もなく、一人ひとりの人間がきちんと尊重されて安らかに生活できているような状態のことを「平和」であると考えるのではないでしょうか。主イエスもそのような地上の平和のことを思って、弟子たちに語りかけておられるのでしょうか。 しかし勿論、いきなり「天の平和」とか「永遠の平和」などと聞かされましても、私たちには、なかなか理解しづらいのではないでしょうか。私たちにとって「平和」とは、地上で見聞きする平和のことしか思い浮かばないのではないでしょうか。本当にそう思うのです。そして私たちが知り得る「平和」というものは地上に成り立つものであるが故に、しばしば非常にもろくも崩れ去ったり、過ぎ去ってしまうような儚いものでしかないということも思わざるを得ません。たとえ今日、戦争が起こっていなくても、明日になれば大国が土足のまま小さな国に踏み込んで来るかも知れません。そういう出来事が今はまだ起きていなくても、次第に緊張が高まり、熱い戦争が起こる遥か前のところでも、人々は不安を感じたり、恐れたり怯えたりしながら生活しなくてはならないことも起こるかもしれません。こういうことは、今日の現実においては至るところで見られることではないでしょうか。あるいは今はまだ経済的な困窮に直面していなくても、現在の社会や世界の情勢がいつまでも同じように続くとは限りません。そんなことを考えますと、この世界に成り立つ平和、地上の平和というのは、いつでもどこかにほころびを孕んでいるような、仮初のものにすぎないことを思わされるのです。 受難週からヨハネによる福音書を読んでいますが、その前まではルカによる福音書を続けて聞いていました。ルカによる福音書では、主イエスが12弟子や72人の弟子たちを、これから主イエスが行こうとされる町や村に遣わしたことが語られていました。弟子たちがそれぞれに遣わされた先は、主イエスもそこに来ようとしてくださる土地でした。主が後からやって来てくださるという約束がそこにはあったのです。 このように考えますと、主イエスがもたらしてくださっている天の平和、永遠の平和とは、別の言い方をするならば、いつどんな場合でも、信じる者一人ひとりが神の顧みと保護の下に置かれ、神に愛され、主イエスに伴われて生きてゆく生活のことなのだと気づかされるのではないでしょうか。地上にはなお戦いがあり、人間の罪の破れがあり、平和もしばしば途絶えがちになります。しかしキリスト者は、そのような死の陰の谷を行く時にも、神によって配慮され、主によって絶えず御言を聞かせていただき、新しい命を与えられて生活してゆくのです。 しかしそれでは、聖霊はどんな働き方をするのでしょうか。14章25節から27節に「わたしは、あなたがたといたときに、これらのことを話した。しかし、弁護者、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊が、あなたがたにすべてのことを教え、わたしが話したことをことごとく思い起こさせてくださる。わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える。わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。おびえるな」とあります。主イエスは既にこの時に、「平和を与える」とおっしゃってくださいました。聖霊は主イエスが話してくださったことをことごとく思い起こさせてくださると教えられています。聖霊によって私たちは、主イエスの語った御言葉を思い起こさせられ、主イエスが共にいるとおっしゃってくださったことも、また私たちが神の顧みの下に置かれていることも、くり返して思い起こさせていただいています。そうやって地上のキリスト者たちは、天の永遠の平和の力をいただきながら、この世界を生きる者とされます。 かつて主イエスが、ベタニアのラザロの死に際して、姉のマルタに「わたしを信じる者は死んでも生きる。生きていてわたしを信じる者はだれも決して死ぬことはない」とおっしゃったことがありました。「死んでも生きる」というのですから、私たちの肉体が不老不死になる訳ではありません。私たちの体には、残念ですが、衰えということが起こります。けれどもたとえ私たちが弱って、また、死の床に横たわるとしても、聖霊が絶えず私たちに語りかけて、神の保護と主イエスの約束を思い起こさせてくださるのです。「わたしは決してあなたがたを孤児とはしない。必ずあなたがたのもとに戻ってきて、あなたと共に生きる」と主イエスは弟子たちに語ってくださいました。その主イエスは確かに復活して生きておられます。その主と共に私たちは生き、主は「神の保護と愛が常にある」ことを知らせてくださいます。私たちは、そのような主の約束を聞かされ、喜んで生きるように今日も招かれています。 最後に、罪の赦しということが23節に語られていますが、これは、神と結びつけられて、感謝し喜んで生きる生活のことを述べています。教会が主イエスの御復活をこの世に語り続け、聖霊がそのことを本当だと分からせてくださるところで、私たちは、自分の置かれている状況に左右されることなく、神の愛のもとに生かされている、永遠の命を生きるようにされてゆきます。 感謝して、そのような神の御業をたたえ、力と勇気を頂いて、尚も今日ここから生きてゆく者たちとされたのです。お祈りをささげましょう。 |
|
