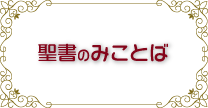ただ今、ヨハネによる福音書20章1節から10節までを、ご一緒にお聞きしました。
1節に「週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た」とあります。新しい週が始まる初めの日、最初に墓に出向いたのは、マグダラのマリアでした。まだ夜は明け切らず、辺りは暗闇に閉ざされています。墓も暗いままでした。死の出来事に関わる場所が、どうして明るいはずがありましょう。しかし、この度失われたのは、マリアにとってはかけがえのない人生の一部です。その思い出をつなぐ場所が墓です。従ってマリアは、墓に出向かずにはいられません。自分の人生からちぎり取られた大切な思い出を、マリアは墓に捜し求めます。
ところがこの日、墓はもはや3日前と同じではありませんでした。マリアはその場の光景に肝を潰します。思い出をつなぐはずの痛ましい記念碑は、すっかり様子が変わっていました。入口を塞いでいたはずの石が墓から取り除けられていたのでした。先にマリアから奪い取られたものが、今度はどこかに持ち去られています。マリアはてっきり、誰かに盗み出されたのだと思い込みます。墓を暴き遺体を持ち去ることは、憎むべき暴挙です。それは死者の尊厳を破壊する行為です。墓の異変に気がついた時、マリアは息が止まりそうだったに違いありません。もしも自分一人だけでこの出来事を受け止めなくてはならなかったなら、彼女は生きていられなかったかも知れません。
マリアにとって幸いだったのは、彼女が経験させられた激しい衝撃を一緒に受け止めてくれる兄弟たちがいたということでした。マリアは一目散にその人々の許に駆けてゆきました。主イエスの一番弟子だったペトロの許へ、また、名前の挙げられていないもう一人の弟子の許へ、マリアは駆け込みました。2節に「そこで、シモン・ペトロのところへ、また、イエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。『主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりません』」とあります。
知らせを受けた2人の弟子も駆け出します。一刻も早く、知らされた事実を確かめなくてはなりません。まるで競走をしているかのように、2人は急ぎます。途中までは一緒だったものの、もう一人の弟子の方がペトロより早く墓に行き着きました。彼は身を屈めて墓の中を覗き込みます。亜麻布が置かれているのを目にしましたが、しかし中に入ろうとはしません。ようやく続いてぺトロも到着し、ペトロはためらわずに中に入ります。ペトロは墓の中を見回して、亜麻布と頭を包んでいた覆い布が別々の場所に置いてあるのに気づきました。その後になって、もう一人の弟子もまた、墓の中に入りました。
この2人の行動には、最初期のキリスト教会の姿が表わされています。ペトロは、ユダヤ人たちからなる最初のキリスト者たちを代表しています。ユダヤ人キリスト者たちが、最初の主の復活の証人です。一方、もう一人の弟子は、多くの国民から召し出されたキリスト者たちを代表しています。いわゆる異邦人キリスト者たちと呼ばれる人々です。そしてこの人々は、二番目の証人というのではありません。彼らは、ペトロに代表されるキリスト者たちを追い抜きます。最初のイースターの日、既にそのところで、「後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」ということが起きています。誰が最初の証人であり、誰が二番かを決めるのは容易ではありません。この2人の歩みは、確かに入り組んでいます。もう一人の弟子の方が先に墓に着きましたけれども、しかし先に墓の中に入ったのはペトロです。
このペトロについては、6節7節に、「彼は中に入り亜麻布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れた所に丸めてあった」と言われています。彼こそが確かな状況を証言できる第一発見者であったかのような書きぶりになっています。しかしもう一人の弟子については、8節で「それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も入って来て、見て、信じた」と述べられています。まるで、ペトロの方は見るには見たけれども信じるところまでは至っていなかったと言っているかのようです。従って、この福音書を書いたヨハネは、2人の競走について、どちらにも軍配を上げていないことになります。どちらかが後れをとったというのではありません。その後、2人は揃って家に帰って行きます。10節に「それから、この弟子たちは家に帰って行った」とあります。
主イエスを救い主メシアと信じる教会の群れは、この時以来ずっと、こんな調子で地上に成り立ってきました。もう一人の弟子が先に信じたような書きぶりだからといって、もはやユダヤ人たちは、主イエスを信じて洗礼を受けることなどあり得ないと考えたわけではありません。ペトロこそが最初に墓の中に入った証人であり、すべてのユダヤ人たちに向けて、主イエスを救い主と信じる者となるように、初めからペトロが居場所を確保してくれています。たとえ今の時代のユダヤ人たちが、その多数が主イエスを救い主だと認めていないとしても、それどころか、今の世界に存在しているイスラエルの政府が無数の人々を迫害し、世界中から批判され、非難されるような暴挙に出ているとしても、それでユダヤ人たちが信仰へと招かれていない訳ではありません。教会は、今ここに集まることできている人たちだけの持ち物ではありません。私たちがここで主イエスの復活を喜び、礼拝を共にささげている時、実はここにいる私たちだけではなくて、今ここにはいませんけれども、やがてこの教会の礼拝に招かれて、共々に主の救いの御業を讃えるように招かれている人たちのための空席が、私たちの間に無数にあるということを知らなくてはなりません。
今日の記事の中で、2人の弟子たちは互いに競い合うようにして墓を目指しています。そして、この2人は一緒に帰って行きます。この2人はそれぞれに個性は違いますが、絶えず一緒にいて、明らかに協力して、主の救いの御業と復活を告げ知らせる群れの中に、他の人たちを招き入れようと努力しました。最初のイースターの日から、教会の歩みの始まりのところから、主イエスの復活を喜ぶ人たちはそんな風だったと言われています。
私たちの間にも、まだ沢山の空席があります。私たちの間に共に座って救い主の御業を喜び、感謝して人生を生きるように招かれている人たちをお迎えするように、先に主を信じるようにされた私たちは、大きな役目を与えられていることを憶えたいのです。実際に招かれる人たちが信仰へと導かれ、私たちの間に共に座り、主を賛美するようになるまで、私たちはここで礼拝をささげ、主に感謝し、賛美し続ける生活に導かれたいと願います。
今日の記事の中で、2人の弟子たちはマグダラのマリアとは違った風にこの墓を見ています。マリアは空の墓を見た途端、墓が暴かれ、彼女にとって大切な方が彼方に持ち去られたと思い込んでいます。一方、2人の弟子たちは空の墓の中に実際に入り、この状況が何を意味しているのか、そのことが分かるまで空の墓の中に佇みます。彼らは決して、この墓が死後の世界につながる通路である思って墓詣でをしているのではありません。古代の権力者たちは、エジプトのファラオであれ、中国の皇帝であれ、日本の大君であれ、生前の生活で必要とした様々なものを墓の中に持ち込み、死後の世界での生活の準備としました。それは、墓の先に自分の人生がつながっているかのように考えてのことです。今日でも、悲しみの中にある方がお墓に供物を携えて行き、その墓の前で亡くなった方との語らいの時をお持ちになることがあります。お墓で、亡くなった方により近づけるように思って、この愛する人が一体どこに行ってしまったのかというやりきれない問いに、せめて僅かの間でも答えを与えられたいと願って、そんな風になさいます。
主イエスの墓は、十字架の死の出来事が完全に事実であったことの証しです。しかし、その墓が今、開け放たれて空になっていることには、二通りの意味が込められています。
第一に、ここにはこの出来事について説明してくれる天使こそ現れませんが、しかし、亜麻布と主イエスの頭を包んでいた覆い布とがそれぞれ別々の場所に丁寧に丸めた形で置かれています。仮にこれが墓を荒らす泥棒の仕業であったならば、そんな状態にはなりません。空の墓の内部がそのように丁寧な状態であったということは、これが人間の仕業ではないことを示しています。
そして第二に、この墓の中に、きちんと整えた形で置かれている亜麻布と覆い布は共に布であり、織物です。ここにも実は意味があります。一つの織物は縦糸と横糸が織りなされて布になります。2人の弟子たちはこの日、墓の様子を注意深く観察し、そして、そこから旧約聖書全体に渡って述べられている事柄を理解し始めます。それはまるで、一本一本の糸から繊物の全体が織りなされてゆくような作業です。空っぽになり、封印が破られて、もはや閉じられることのない空の墓の中に、今、彼らはいます。この空の墓そのものが旧約聖書の約束を読み解く鍵となるのです。そのことを表すために、9節に注意書きが添えられています。「イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである」。この注意書きによって、理解する方向が指し示されるために、こう書き込まれています。
2人の弟子たちは、今自分たちが置かれているこの局面から理解し始めます。まず彼らは外から中を覗き込みます。次に、彼らは空になった墓に入り、辺りをよく見つめます。そして最後に、彼らは起こっている出来事を理解し始め、信じるようになります。信じて、さらに理解が深まるようになります。閉じられたままで読まれずにいる聖書は、その中に言葉がぎっしりと詰まった墓のようなものです。開かれないなら、聖書は単なる記念品でしかなく、神の言葉の墓のようなものにすぎません。しかし、いったん聖書が聞かれて、聖書を織りなしている一筋一筋の言葉の糸目を凝らして読み進みますと、私たちは、神が私たちのために成し遂げようとしてくださる救いの御業に触れることができるようになり、そして御言を通して神の御業を少しずつ理解するようになるのです。
先々週と先週、私たちは聖書全巻を皆でリレーして通読しました。特に最初の方の旧約聖書を読んでいた方は、そこに記されている文字を読み取ることはできても、それらの言葉がどこに向かって行くのかが分からず、まるで雲をつかむような話を聞いているような思いになったかもしれません。聖書全体の言おうとしていることはどうも分からないと最初から諦めてしまって、聖書を開いて御言に聴こうとする営みを退けてしまうようなところが、私たちにあるかも知れません。
けれども聖書全体がどこに向かっているのかと言えば、まさに今日私たちが耳にしている、この空の墓から解き明かされて行きます。聖書全体は、この空の墓に向かって記されています。もちろん、このことを決して認めようとしないで、未だに旧約聖書だけが聖書であると考える人たちもいます。しかしそういう人々は、聖書全体を一枚の布として見るのではなく、無数の言葉の糸が一本一本ばらばらに聖書の中に詰まっていると考えて、そして、その言葉一つ一つに従って生活しようとします。ユダヤ教の読み方は、そのような読み方です。けれども私たちは、この開かれた墓が、聖書全体の向かっている救いの御業であることを知らされています。神の救いの御業は、この空の墓にこそ向かって進んでいました。そして、ここから始まって、私たちが今生きる営みにまでつながっているのです。
ヨハネによる福音書は、復活の出来事を天使の口を通じて証言させる代わりに、2枚の織物、即ち大きな亜麻布と主イエスの頭を包んでいたそれよりも小さい覆い布がきちんと丁寧に置かれていたことを通して、私たちの前に2冊の聖書を示し、神の福音全体がこの空の墓から始まる大きな物語であることを伝えているのです。
このヨハネによる福音書のイースターの記事から聞こえてくるのは、初め、墓の様子を見に行ったマグダラのマリアが異変に気づいて途方に暮れたことや、その知らせを聞いた2人の弟子たちが競走するように墓まで駆けて行ったこと、また墓の中に入ったペトロが最初はマリアと同じように途方に暮れたという姿です。しかしもう一人の弟子については、そこにはペトロも含まれてゆくのですが、「見て、信じた」、「それから、この弟子たちは家に帰って行った」のでした。2人の弟子は、信じる者となって、家に帰って行きます。彼らは、神が主イエスになさったことを信じます。死者の中から新しい命の許へと、主イエスをよみがえらせてくださったことを信じて、2人は家路に着くのです。最初から神のなさりようについて、すべてのことを了解できていた訳ではなかったのです。しかしそれでも、今ここで、神が主イエスを復活させてくださった、そしてここにこそ救いの御業が起こっていることを信じて、家路に着きます。9節に述べられている「主イエスの復活について語っている聖書の言葉を二人はまだ理解していなかった」という言葉は、この2人がこの後、この方向で復活を信じ、聖書の言葉全体をいよいよ深く理解していく、その端緒、糸口を与えられて家路に着いたことを述べているのです。
ところで、今日の記事の最初に登場していたマグダラのマリアだけは、2人のようには空の墓の出来事を理解できないままに、いわば取り残されたようになっています。主イエスはしかし、御自身の愛する者たちがそんな風に無理解と悲しみの中を彷徨い歩くことをよしとなさいません。それで、このすぐ続きのところで、主イエス御自身が悲しんでいるマリアの許を訪れてくださり、死や悲しみや虚無の絶望が終わりの事柄ではないことを知るようにしてくださいます。
このようにして、今日、私たちは、主イエスが復活の初穂となっていてくださり、すべての者が、たとえ今はここにいなかったり敵対していたり、無関心だったりするとしても、それでも主の愛のうちに憶えられていることを信じるように招かれています。
その招きの中で弟子たちは、主イエスがかつて教えてくださったように、「わたしが生きているので、あなたがたも生きることになる」ことを信じる者とされてゆきます。そして弟子たちは、主イエスの復活を信じて、再び家路に着くのです。
私たちもこの日、そのように主に変えられてゆくと信じて、ここからの一巡りの歩みに進む者とされたいのです。お祈りをささげましょう。 |