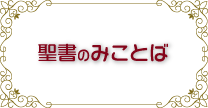ただ今、ルカによる福音書12章1節から3節までを、ご緒にお聞きしました。
1節に「とかくするうちに、数えきれないほどの群衆が集まって来て、足を踏み合うほどになった。イエスは、まず弟子たちに話し始められた。『ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である』」とあります。実に多くの人が主イエスの許にやって来たことが述べられています。「数えきれないほどの群衆」と言われていますが、原文でここには「無数の」とか「1万の」とか訳せそうな言葉が記されています。1万人もの人が集まれば、確かに数えきれないに違いありません。そんなに多くの人が集まって来て「足を踏み合うほど」であったと言われています。当時の状況の混乱ぶりが伺えるような言われ方です。数え切れないのですから数字を言うのも変なのですが、仮に1万までではないにせよ、数千の人が一つのところに集まるとなると、誰がどこにいるのか見当がつかなくなるに違いありません。主イエスの許にやって来た人々も、そんな状況に立ち至ったのでしょう。群衆は、元々は主イエスを目指してやって来たはずなのに、あまりにも人が多くて、人混みの一体どこに主がいらっしゃるのか分からなくなっています。主イエスの言葉、主イエスの声を聞きたいと願っても、どちらに向かって耳を澄ませたら良いのか、分かりかねるような状況です。
最初は主イエスにお会いするつもりでやって来ていても、このような無数の人々や混雑した大群衆を前にしては、何のためにここに来ているのかが分からなくなってしまったり、考えや思いが変わってしまうような人も出てきそうです。実際この少し先の箇所には、集まって来た人たちの中から、親の残してくれた遺産の分配をめぐって自分に有利となるように計らって欲しいと主イエスに願い出た人のあったことが語られたりします。おそらくその人は、最初からそのような目的でやって来たのではなかったでしょう。主イエスの許にせっかく大勢の人が集まって来ても、それで良いわけではないようです。その中で、何のために自分がここにやって来たのか、何のためにここにいるのかが分からなくなっている人たちが大勢いる様子なのです。
そのように混乱を極めている状況の中で、主イエスはまず、御自身の近くにいる弟子たちに呼びかけて教え始められました。そこで最初におっしゃったことが、「あなたは、ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である」ということでした。「ファリサイ派のパン種」とは、どういう意味でしょうか。主イエスは、「それは偽善である」と分かり易く教えてくださっています。しかし、この「偽善」というのはどういうことでしょうか。ごく簡単に考えるならば、周りの人たちから良く見てもらうために、自分を実際以上に良さそうに見せることが偽善であると言えるかも知れません。
しかしそれならば、主イエスは弟子たちに、どのようなあり方をするように望んでおられるのでしょうか。実際以上に自分を良く見せかけようとするのが悪いというのなら、そのように周囲から見られないようにわざと自分を卑下して見せたり、あるいは周囲から注目されないように一歩退いて、自分の本来の姿が周囲から分からないように隠れて生活するのが良いことなのでしょうか。いわゆる韜晦(とうかい)とか隠遁とか呼ばれるような生き方です。主イエスはそんな風に、いかにも勿体ぶって生きるようなあり方を弟子たちに教えようとされたのでしょうか。そうではないようです。「偽善に注意するように」という教えは、深く考えずにこれを受け取るならば簡単に分かるような気もするのですが、しかし、改めてこの話で主イエスが弟子たちにも私たちにも求めておられる「あるべき姿」がどのようなものかと考えてみますと、私たちはふと分からなくなってしまうのではないでしょうか。
そもそも、この偽善の事柄がファリサイ派のパン種であると言われるのはどうしてなのでしょうか。どうして偽善がパン種なのでしょうか。周囲が大いに混乱した状況にあった中で、主イエスがまず何よりも先に弟子たちに教えようとなさった事柄をしっかりと理解して受け止めるために、今日はここで主が口になさった偽善という言葉に思いを向けて考えてみたいのです。主イエスが注意するようにと警告してくださっている偽善という事柄が、果たしてどのようなことなのかに思いを向けて、この言葉をしっかりと私たちの心の内に刻みつけたいのです。
「偽善」と日本語に訳されている言葉は、別の言葉に訳すこともできます。ここで「偽善」と訳され、また時には「偽善者」と訳される言葉は、別に訳すと「俳優」、即ちお芝居に登場する「アクター・アクトレス」とも訳される言葉なのです。しばしば言われることですが、当時のお芝居では、俳優たちは自分の素顔を見せて芝居をしたのではありませんでした。俳優たちが演じるそれそれの役割ごとに、木で彫られたお面が用意されていて、俳優たちはそのお面を被ってセリフを語り、演技したのです。悲しい芝居、いわゆる悲劇では、木彫りの面は沈痛な面もちに彫られており、また面白おかしく喜劇に使うお面は、滑稽な顔に彫られていました。俳優たちは自分自身の生まれついた素顔を晒すのではなくて、お面を被って役割を演じて見せたのでした。お面を被った俳優たち、役者たちという言葉が、ここに記されていて、そしてそれが偽善者、偽善と訳されています。
つまり、お面を被って芝居を演じて見せる役者たちのようなあり方がここでは偽善であると言われていて、主イエスは弟子たちに向かって、「あなたたちは、そのような上辺の見せかけだけのあり方をしないように注意しなさい」とおっしゃっているのです。
では何故、そのような上辺のあり方を表す偽善がファリサイ派のパン種だと言われているのでしょうか。パン種というのは、実際にパンを手作りなさる方にとっては非常に身近にあるものですが、小麦と水をこねて作ったパン生地に加えるイースト菌のことです。生地にイースト菌を加えて、常温で一定時間寝かせますとパン生地へ中でイースト菌が発酵して炭酸ガスが生まれ、それが生地の中に入り込んで無数の小部屋が生まれ、生地全体がふっくらと膨らんできます。それを焼くとパンになる訳で、イースト菌は柔らかいパンを焼く上では欠かせない大切な存在です。
しかし主イエスがここで使っておられるパン種という言葉は、そういう良い意味での使い方ではありませんで、むしろここでは悪い意味を表しています。役者たちが仮面を被って演じる芝居では、観客は役者自身の顔ではなくて、一番外側のお面の顔を見て泣いたり笑ったりすることになります。しかし仮面の下では役者は、いつでもどんな顔でもしておれますし、仮面の下の顔がどのようであっても、観客はそこには気づかないのです。ファリサイ派の人々が好んで演じて見せた顔はどのような顔だったかというと、神の事柄に対していつも真剣に向き合い、掟を守って生きようとしている、そういう敬虔な顔です。そういう側面を周囲に見せることで、ファリサイ派の人たちや律法学者たちは当時のユダヤ人共同体の中で深く信頼され、尊敬もされました。人々はファリサイ派の人たちの上辺を見ていたからです。
ところが、主イエスが御覧になるのは上辺だけではありません。心の内も御覧になっています。ファリサイ派の人たちが、いかにも敬虔そうに見せる上辺の姿をいわば隠れ蓑のように用いながら、しかしその人の中にどんな思いがあり、どんなに物騒で下品で危険極まりない考えがその人の心の中に思い浮かんでいるかということを、主イエスは見抜かれます。ファリサイ派の人たちは上辺の敬虔そうに見えるあり方を周囲の人たちから褒められれば褒められるほど、本人の心の内では自分というものがどんどん大きく膨らんでいきます。神に対する平らかさや神を畏れるあり方がなりをひそめ、むしろパン種がパンを膨らませるように、その人の傲慢な思いや高ぶりが大きく膨れ上がってしまうようになります。人々に向かっていかにも敬虔そうに見せかける上辺を飾るあり方は、その時点で周囲の人々を欺くだけでは終わらず、むしろ、敬虔そうに見せる仮面の下で、人間の高慢と神抜きで生きようとする頑ななあり方がどんどん膨れ上がり、大きくなってしまうのです。ですから主イエスは、偽善を、ファリサイ派が好むパン種だという言い方で説明なさいました。
ところで、主イエスがこのようにおっしゃったのは、ファリサイ派の人々の一見敬虔そうに見せている仮面の下に、どんなに物騒なものが隠れているかということを暴露してそれを白日の下に晒し、辱めを与えるためだったのでしょうか。それとも、弟子たちがファリサイ派と同じような誘惑に負けてしまわないように戒めるためでしょうか。
今日の箇所では、大勢の群衆が押し寄せ、大方の人には主イエスがどこにおられるのか分からず、主の声に耳を澄ますこともできないようになっている状況の下で、主イエスはまず弟子たちにお語りになったのだと言われていました。そうであるならば、ここで主イエスがおっしゃっているのは、ファリサイ派のあり方を腐したり貶めたりする目的ではなくて、主イエスの言葉に耳を傾け聞こうとしている弟子たちに向かって、警告として語られた言葉ではないでしょうか。つまり、大勢の人たちが群がり収拾がつかなくなっている世の中にあって、主がここにおられることを理解し主の言葉に聞き従おうとする者たちに対して語られている戒めの言葉だということになるでしょう。主イエスはここで、世の中のファリサイ的なあり方を批判して嘆いておられるのではないのです。御自身の声を聞き分けることができる、御自身が招こうとしておられる羊の群に向かって、いわば主イエスが羊飼いのように語りかけてくださっているのが今日の箇所です。「あなたがたは偽善に注意しなさい。それは敬虔そうに見せかけていて、しかし、神の御声に聞き従って平らに生きることからあなたがたを引き離し、神のことを如何様にでも考え扱えるようにあなたがたに思わせてしまう恐るべき危険な罠なのだ」と、主イエスは警告なさいます。ファリサイ派のパン種はファイサイ派の人たちだけの問題なのではなく、キリスト者にとっても決して無縁のものではなく、むしろ、真剣に神に従って生きようとする信仰者の人間的な思いの中に入り込み易い危険であるとさえ言えるのです。
今日の箇所では、主イエスはパン種に気をつけるようにと弟子たちを戒めておられますが、たとえば時代が下り、パウロがコリントの教会に宛てて書いた手紙の中には、実際にこのパン種が教会に生きるキリスト者たちの間に入り込んでその生活を蝕んでいたらしい形跡を見ることができます。コリントの信徒への手紙一5章6節から8節に、「あなたがたが誇っているのは、よくない。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませることを、知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現に、あなたがたはパン種の入っていない者なのです。キリストが、わたしたちの過越の小羊として屠られたからです。だから、古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない、純粋で真実のパンで過越祭を祝おうではありませんか」とあります。
ここでパウロが語っているパン種は、今日の箇所で主イエスが警告して弟子たちを戒められたのと同じ、悪い意味でのパン種です。主イエスはそれを偽善だとおっしゃいましたけれども、その偽善の仮面の下で大きく育った高慢さや虚栄心について、パウロは戒めています。「自分たちには、そのような悪いパン種は相応しくない。それを捨ててしまいなさい」と勧めています。「古いパン種をきれいに取り除きなさい」とパウロは言います。「何故なら、あなたがたは現に、そういうパン種の入っていない者とされている」、「キリストが私たちの過越の小羊として屠られた」、これはキリストの十字架のことを言っているのですが、「キリストの十字架によってあなたの罪は赦され、新しいパン生地とされ、今を生きるようにされている。あなたたちは、種入れぬパンとして過越の祭の祝いに招かれているのだ」とパウロは教えています。「主イエスが十字架の上に御自身をささげてくださったことで、あなたがたは神の前に生きる清い者とされているのだから、悪い古いパン種を捨て去って、招かれている新しい道を歩きなさい」とパウロは語ります。「本当に清らかな嬉しい生活があなたがたには与えられているのだから、自分をごまかしたり、飾ったり、上辺を見せかけたりしないで、感謝して主イエスに仕える生活を生きてゆこう」という招きが、パウロからコリント教会に向かって語られています。
主イエスもまた今日のところで、偽善的なあり方に陥らないようにと弟子たちに戒められた後、パウロが語ったのとまったく同じ事柄、つまり、神の御前に生きる新しい生活が与えられるという約束についてお語りになっています。2節3節に、「覆われているもので現されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だから、あなたがたが暗闇で言ったことはみな、明るみで聞かれ、奥の間で耳にささやいたことは、屋根の上で言い広められる」とあります。「覆われているもの」とか「隠されているもの」とか、いかにも思わせぶりな言い方に聞こえますが、これは救い主として来られた主イエスの御言葉です。そして主イエスが弟子たちに知らせてくださった神の救いの御計画なのです。
主イエスはこれまでのところでも、またここからのところでも、繰り返して、御自身が救いの御業を地上において最後まで果たすため、敵の手に引き渡され十字架につけられるのだということを、まったく包み隠さずに弟子たちに告げてくださいます。ところがその度に、「弟子たちには、聞かされた言葉が分からなかった。理解できないように彼らにはその言葉が隠されていたからである」と語られます。しかしそれは最終的には、「隠されていたことは明らかに現され、明るみで言い広められるようになる」のです。
主の十字架の予告が何度も繰り返して語られたのと同じように、弟子たちにとって覆われ隠されて今はよく分からないように感じられる主イエスの十字架による救いの言葉が、やがて明らかに知れ渡るようになるということも、主イエスは繰り返し弟子たちに語っておられました。「覆われているもので現されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない」という2節の言葉は、この福音書の中で、これまでにも聞いた言葉です。8章17節でも、言葉は少し違っていますが同じことが語られています。「隠れているもので、あらわにならないものはなく、秘められたもので、人に知られず、公にならないものはない」と教えられています。
主イエスは御自身を救いのための供え物として十字架上にささげてくださり、私たち人間の罪をすべて御自身の側に引き取ってくださり、その死によって私たちの罪を清算してくださいました。そのことによって私たちは、神の御前に清められた者とされ歩み出すことが赦されました。そうであるのに、主イエスに委ねず、これは自分の問題だから自分の人生の中で決着をつけるのだと言って、私たちが主イエスの十字架を自分のこととして受け取らないならば、私たちは自分の抱えている罪の問題を最後まで解決できないまま終わってしまいます。どんなに真面目に、敬虔に生きようとしても、結局はファリサイ派のパン種、偽善の姿にしかなれない、私たちはそういう惨めなところを抱えているのです。
だからこそ神は、主イエスを送ってくださって、十字架の御業をなしてくださいました。十字架によって私たちは、神の御前に清められた者とされました。パウロの言葉で言うならば、古いパン種が主イエスによって取り除かれて清められ、パン種の入っていない新しい生活を生きるようになるのです。
そしてそのことは、私たちが「本当だ」と信じて生きるならば、たとえ暗がりの中で小声で言い表した覚束ないような信仰の言葉であっても、その言葉を神は喜んで聞き上げてくださり、喜びいっぱいの教会の賛美の一部として、高く言い広めてくださるのです。「だから、あなたがたが暗闇で言ったことはみな、明るみで聞かれ、奥の間で耳にささやいたことは、屋根の上で言い広められる」と主イエスは言われました。
主イエスは、私たちの上辺のありようではなく、実際のありようを、私たちがしばしば犯す失敗も皆、御覧になります。そして私たちの中に、神が主イエスによって行ってくださった救いの御業を喜び感謝して生きようとする信仰が宿っていることを御覧になって、主もまた喜んでくださるのです。私たちはそのようにして、主イエスから憶えられています。そのような主イエスの前で、私たちが上辺だけを飾り、敬虔そうに見せようとすることの意味が果たしてあるでしょうか。
今日の箇所で、主イエスは旅の途上におられます。私たち人間のために救い主として十字架にかかるという決心を持って、ゴルゴタの丘を見据えて道を進んで行かれる主イエスがいらっしゃいます。その主イエスが、「あなたがたは上辺の見せかけではなく、心の底から、あなたのために行われるあの十字架の救いの御業を見上げ、これに砕かれて、新しい人に変えられるように」とおっしゃってくださいます。
私たちはその十字架の上を見上げ、私たらのために果たされた救いの御業を仰いで、パン種とは関わりのなくなった新しい者に作り変えられることを信じて、祈りながら、感謝し喜びをもってここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。 |